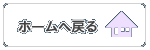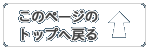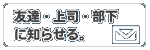第15話 デルタ大学、裏口入学2011年11月9日(水曜日)
アメリカにはさまざまな大学がある。
スタンフォード大学やハーバード大学のような私学。
カリフォルニア大学やオレゴン大学など、州の名前はつくが、州立と言わない、どちらかと言えば連邦政府が設立した大学。
カリフォルニア州立やオハイオ州立など、州政府が設立した大学。
この他にも、州に中にある郡 (County・カウンティ)が設立運営する、ジュニア・カレッジ(コミュニティ・カレッジ)がある。
当時は希望すれば、ジュニア・カレッジには、誰でも入学することができた。
日本で四年制大学を出た人たちは普通なら大学院に向かう。
ジョージ君は英語力がなくても志の高い人は、英語を勉強後、大学院を目指すのが正当だと考えていた。
英語力も自信もなく、怠惰で目的が明確でない人は、高卒が入るジュニア・カレッジを狙った。
ジョージ君の住むストックトン市は豊かな農業地帯で、外国人留学生は授業料免除の奨学金がもらえた。
カリフォルニア州には当時、60数校のジュニア・カレッジがあったが、外国人留学生に授業料免除の奨学金を出すのは、ここストックトンと、北へ3時間ほど行ったところにあるチコ市のジュニア・カレッジのみであった。
中古車に金を使ったジョージ君は、授業料に回す金は無かった。
入学できなければ、帰国か非合法外人の不法滞在しかない。
しかし帰国はできない。
不法滞在もしたくない。
ジョージ君は奨学金付きのデルタ大学の入学試験を受けた。
ミシガン・テスト(英語力判定試験)が145点以上なら入学の可能性があったが、会社派遣のエリート留学生、前田氏でも138点しか取れなかった。
ジョージ君のテスト結果は84点、不合格だった。
予想どおりである。
その日、ホームステイ先での食事中、浮かない顔のジョージ君に奥さんのベティーが気付いた。
「ジョージ、何か悩みがあるの?浮かない顔よ」
「えぇ、デルタ大学に入れなかったら、授業料も払えないので帰国しないといけない。外国人相手の奨学金がもらえなかった・・・」などと、詳しく事情を話した。
ベティーは最初、難しい顔をしていたが、やがて言った。
「そんなこと、簡単なんだけどな…。学長はブランチャード博士でしょう?私の父はMR.STOCKTONよ。彼なら何でもできる。私も頼みたくはないが、聞いてあげるわ。明日、彼のところに行こう」
翌日、ランチと昼寝が終わったころを見計らって、アートン邸に行った。
後妻のイタリア人女が、何しにきたのかと、好奇心丸出しの顔を見せながらも、そっけない言葉で迎えた。
ベティーはジョージ君に言った、「あいつは嫌いだ」
ジョージ君から見ても、想像していたような“イタリア国からきたお嫁さん”という感じではなく、イタリアの女中のおばさんにしか見えなかった。
何を好んでこの大富豪が彼女を嫁にしたのだ?
アートン氏は体格も良く、インテリ風、かつて権力を欲しいままにしていた貫禄があった。
ジョージ君は緊張していた。
ベティーは久しぶりに会った父なのに、雑談はなく、事務的だった。
「要件というのは、この日本人を奨学金付きでデルタ大学に入学させて欲しいの。学長はブランチャード博士、パパの軍隊時代の部下でしょう」
「何のために俺がそんなことをしないといけないのだ」
「私たちはジョージが好きなの。信用できるし、彼が必要なの。入学できないと日本に帰ってしまう。でも、それは困るのよ。従順な日本人の特性をパパも知っているでしょう?」
「じゃー、それはお前のためになるんだネ。それなら電話をしてやろう」
「ハイ、ドクター・ブランチャード。俺だ、アートンだ」
電話から聞こえてきた。
「Yes, Sir」
「ここにジョージという日本からの入学希望の学生がいる。奨学金をつけて入学させてやれ」
「彼なら知っています。何度も私の事務所にきましたから。彼は日本の大学を出ています。しかしこの学校は、四年制大学に入る前の一般教養を勉強させるところ。彼には入学資格はありません」
アートン氏はベティーの顔を見た。
ベティーは目で合図をした。
“パパ、それでもお願い”と懇願している、そんなそぶりだった。
アートン氏は言った。
「そんなことは百も承知だ。私の娘がジョージを必要としている。そのために君の力が必要だ。いいか、これはお願いではない。This is my order、私の命令だ」
「Yes Sir、My Boss. すぐここに来させてください」
ジョージ君にとって、映画を見ているよう不思議な光景だった。
アメリカでも権力やコネで無理が通る。
これは凄い。
本や雑誌、教科書では知らなかったアメリカを体験していた。
入学が許可されたのだ。
ジョージ君はすぐ学校に行った。
ブランシャード博士は、イライラしながら立って待っていた。
会うなり、ジョージ君を怒鳴りつけた。
「誰の知恵だ。汚たない手を使う奴だ。憶えていろ」と言いながら、I-20 VISAの書類をジョージ君の顔に投げつけた。
書類は床に落ちた。
ジョージ君は書類を拾い、ブランチャード博士に手を差し出して「Thank you, Sir.」と握手を求めた。
ブランチャード博士も言いたいことを言って、少しは落ち着いたのか、手を握り返した。
「Good Luck」
このあたりはアメリカ人の良いところで、ジョージ君の好きなアメリカであった。
しかし、このI-20 VISAには落とし穴があった。
短大を卒業するのに必要な2年分ではなく、1セメスター(学期)、期限が半年分しか書いてなかったのだ。
半年後、「君はここの学生ではありません」と、手紙がきたのである。
ブランチャード博士にやられたと思った。
ジョージ君はこの程度ではあきらめなかった。
こんなことで日本には帰らない。
ジョージ君には再び、漲るような力が湧いてきた。
困難にあたると猛然とファイトが出る。それは日本人のせいだと思えた。
困難こそ、日本人に生まれた喜びを感じる瞬間、日本人が忘れた大和魂を意識する時だった。
嫌がるベティーを説得し、またアートン氏を動かした。
さすがに、この時のブランチャード博士は紳士的だった。
自分の意地悪を多少、後悔したのか?このしつこい日本人に呆れたのか?は知らない。
残りの3セメスター分のビザの延長に同意した。
やがてクリスマス・シーズンがきた。
サンフランシスコの日本人街に行って、和風のクリスマス・プレゼントをホスト・ファミリー全員とアートン氏に買って渡した。
やがて正月も終わり、3週間ちかく経ったある日、ベティーがジョージ君に突然言った。
「私のパパが君を嫌っている。クリスマスの時、私の父に何を渡した?」
「日本の富士山を描いてあるカレンダーと日本人形を渡した」
「それはいくらの価値があるの?」
「100ドル」
「私の父が怒るのがわかったわ。君は最終的に授業料をいくら節約した?」
「2000ドル少々」
「それならその半分を現金で持って行け」
ジョージ君にとって目からウロコだった。
アメリカを甘く見ていた。
「私もそうしたいが、金がないので、アートン氏にそのようなお返しはできない。いつの日か、出世したらお返しをしたい」
彼女はせせら笑った。
「君は決してそんなことしないだろう。
人間は、今はそのように思っていても、実際は将来そのようにしないものだ。
出世払いなど笑わせるな。信じられるか。
感謝をしているなら、今すぐ現金で持って行け。金がなければ、親から借りるなり、なんとでも工面をしろ。それがいやなら彼に労働力を提供して返すことだ」
大金持ちたちのこの理論にジョージ君は怯んだ。
しかし、無い袖は振れない。
「では労働力でお返しします」と答えざるをえなかった。
翌日、日系人の救世主と言われた、ハンバーガー先生に相談に行った。
ドイツ系、金髪の彼女は元デルタ大学の英語の先生で、一生独身を通し、人権問題の向上だけを目指し、生きた、信念の塊のような人だった。
特に第二次世界大戦の前後は、善良で正直で勤勉な日本人の人権と権利のために戦った人だった。
アメリカの公平、平等、ひとり一人の幸福の追求という、アメリカ憲法の理想のために戦ったとも言える。
ジョージ君は彼女に事情を話した。
ハンバーガー先生は70歳を越えていたが、まだカクシャクとして元気だった。
「ジョージ、ごめんね。君が体験していることは、アメリカのすべてではない。不幸な体験をしたね。
アートン弁護士はよく知っている。彼は戦前、日系人排斥法案を通すことにさも熱心な法律家だった。娘のベティーは大富豪の苦労知らずの我がままな娘さ。ハイドン氏がベティーの夫になったと聞いた時、それはそれは驚いた。お似合いの夫婦だ。
ハイドン氏は体は小さいが、フットボールの選手で喧嘩早く、学校では番長だった。
君はよくそんな家庭にホームステイをしているね。彼らは普通のアメリカ人ではない。とにかく、奨学金の半分を現金で返せなど、とんでもない話だ。無視しなさい」
ジョージ君はハンバーガー先生の言葉に安堵した。
「ありがとうございます。」
しかし、ハンバーガー先生のような考え方はむしろ少数派だとも思った。
アメリカの一般人、特に成功者、金持ちたちはむしろ、ジョージ君のホスト・ファミリーのような考え方をしていると思えた。
アメリカ社会や世間は甘くない。
日本の社会経験のあるジョージ君には、そのことが痛いほどわかった。
この話には後日談がある。
ジョージ君が、サンフランシスコの金門橋を越えた景勝の地、サルサリートの小さな教会で結婚式を挙げた時、ホスト・ファミリーは大勢でやってきた。
ベティーはジョージ君に言った。
「おめでとう。でも結婚の祝いはなにも無いよ。君は我々にまだ恩返しをしていない。今日はタダ飯を食うためにきた、借りを取り返すためにきたんだ。解るか?ジョージ」
「もちろんですよ、あなたは私のアメリカにおける、人生の先生です」
それにしてもすごい。
めでたい結婚式に、堂々と「タダ飯を食いにきた」と言い切る凄さ。
日本の防衛のただ乗り批判や、平和、繁栄をもたらしてやっているのだからそれなりの負担をしろというアメリカ人の心をここで知ったのである。
ホスト・ファミリーには、心から感謝したい。
そして、アートン氏にも恩返しはしていない。
結局、ベティーが言ったことは正しかったのだ。
甘えるな、日本人ジョージ君!