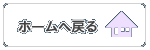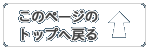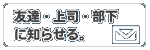第36話 マービンとの乱闘2012年4月20日(金曜日)
ジョージ君がキャサリンの信頼を得るにつれ、キャサリンの娘マービンとの関係が怪しくなってきた。
キャサリンとマービンは以前からたくさんの問題を抱えていたので、ジョージ君は最初、自分は部外者だと思っていた。
ところが、マービンが日本人は大嫌いだと公言するようになり、風向きが変わった。
しまいには「日本製品も、日本に関するすべてが嫌いだ」とキャサリンに訴えはじめた。
会社は日系2世の会計士AKIに乗っ取られ、家庭はジョージ君に乗っ取られ、と考えたらしい。
ジョージ君はマービンに言った。
「そこまで日本が嫌いなら、君はダットサン280Zに乗るのをやめたらどうだ」
「どうして、私がダットサン280Zに乗るのをやめないといけないのよ」
「ダットサンは日本製だ」
マービンは応じた。
「ジョージ、違うよ。あれは日本製ではない。私が物心ついた時からすでにある」
「それもそうだ。そう思っても無理もない」とジョージ君はつぶやいた。
キャサリンが言った。
「あの娘は無知だから、ダットサン280Zが日本製であることは知らないのよ」
そこでジョージ君は、今度はキャサリンに尋ねた。
「ところでキャサリン、いつも飲んでいるネスカフェを作ってる会社はどこの国の会社だか知ってる?」
「あれはアメリカの会社よ」
「違う、ネスレはスイスの会社だよ」
「でも昔からあるのに…」
人間の知識なんてそんなものだった。
新参者のジョージ君の存在は、マービンにとって相当目ざわりのようだった。
やがてキャサリンが出張の時は、同級生のボーイフレンドを母親のベッドに連れ込むようになった。
学校も行かなかった。
一晩中大声をあげ、時には二人で屋敷中を裸で走りまわっていた。
ジョージ君の目の前で急に立ち止まったり、変にバカにしたように、裸を見せ、股をひらいたり、笑ったりしていた。
それにしてもその馬鹿ヅラと、水泳と乗馬で鍛えられた抜群のスタイルは、見事にアンバランスであった。
二人はいつもジョージ君を挑発していた。
ジョージ君が大学から帰っても、二人はまだキャサリンのベッドルームで寝ていた。
ベティーの家といい、キャサリンの家といい、アメリカの富豪の家はジョージ君には信じられない世界だった。
まず、親子の信頼関係は無きに等しかった。
いくらアメリカでも、これは普通ではない。
それぐらいはわかっていた。
彼らが部屋から出ると、豪華なベッドルームは戦争の跡のようであった。
その上、台所は汚し放題、冷蔵庫の物は出しっぱなし。
野獣が食べ散らした後と同じだった。
キャサリンはいつも彼女のことをANIMAL(動物)、あるいはMAD GIRL(狂った娘)と、叫んでいるのがよく理解できた。
ジョージ君は最初のうちはキャサリンが帰ってこない日でも必ずベッドメイキングはしたが、そのうち、彼女がいない日には何もしなくなった。
マービンが汚した跡を綺麗にする意欲は失っていた。
それでも、キャサリンが帰ってくる時は完璧な状態で迎えようと努力した。
しかし、やがてそれすら不可能になってきた。
マービンは2匹の大型シェパードをベッドルームに入れて寝ていた。
最初の頃は二人が寝ていても、ベッドルームのドアを叩くと、ドアをあけて犬を出してくれた。
やがて彼らはジョージ君がドアを叩いても、起きてこなくなった。
マリワナのせいだ。
一日中閉じこめられた大型犬はドアから出られず、2匹の犬はオシッコと糞をあちこちにした。
ピンクのカーペットはたちまち汚れた。
ジョージはその糞を取って、掃除をしたが、完全に汚れは落ちなかった。
マリワナの匂いが部屋中に充満していた。
キャサリンは帰るやいなや、烈火のごとく怒り狂い、ジョージ君を怒鳴った。
ジョージ君はキャサリンがいない日に何が起こっているのかを克明に報告した。
学校からもマービンが頻繁に学校を休んでいるとの手紙がきていた。
マービンはいくら叱られても、悪びれもせず、平気な顔をしていた。
キャサリンに愛されない復讐劇でもしているようだった。
キャサリンはジョージ君に頼んだ。
「ジョージ、これからは何があっても、朝には犬たちを出して欲しい。久しぶりに家に帰って、私の部屋がここまで汚れていると、本当に絶望的になる」
それでもキャサリンは強気だった。
ジョージ君はこの親子関係に対して絶望的な気持ちになった。
もはやこれは家族ではない。
敵同士だ。
身長178センチのマービンは、いつも10cmのハイヒールを履き、ジョージ君を見おろしていた。
ジョージ君のことを明らかにバカにするような顔をしていた。
マービンがジョージ君の言うことを聞くとはとても思えなかった。
まして憎しみは、母親にだけでなく、その母親に気に入られたジョージ君にも向けられていたのだ。
キャサリンは次の出張に出た。
その日はジョージ君の授業は午後からだった。
朝の9時にドアを数回叩いた。
「マービン、ドアを開けろ。」
返事はない。
15分後にまたやろう。
繰り返し、繰り返し、10時まで根気よくドアを叩き続けた。
犬の悲鳴が聞こえてくる。
明らかに用を足したいのだ。
学校に行く時間も迫っていたので、ジョージ君は今度はドアを叩きながら、大声で叫んだ。
「マービン起きろ、犬が外に出たがっている。早く、早くしろ!」
ドアを打ち破ってでも開けさせる気持ちでいた。
しかし、ドアは開かない。
ジョージ君も意地になってきた。
彼らがとても寝ていられないような大声で、しかも日本語で叫んだ。
「テメー起きやがれ、オンドリャ、いい加減にせんか?」
やはり、関西弁だった。
英語なら「Fuck You, Ass holeとかShit」と叫びたかったが、ダーティーな(汚い)英語はどうも使い慣れない。
こういう時はやっぱり関西弁が一番だ。
突然ドアが開いた。
するといきなり、パンティー一枚でハイヒールを履いたマービンが、ジョージ君の顔に向かって右足で前蹴りをしてきた。
明らかにヒールを凶器として利用しようとしていた。
殺気を感じた。
ジョージ君の体は本能的に左に動いた。
蹴りをかわした。
空手のように腕でブロックをすれば、腕が折れる。
当っただけだとしても、ヒールで腕が切れる。
顔に当たれば、顔面骨折、腹なら内臓破裂もあり得る。
体をかわし、左手で彼女の足を右の方向に押した。
彼女はバランスを崩して倒れた。
しかしすぐに起きあがり、右手で殴ってきた。
ハイヒールを履いた背の高い彼女が覆いかぶさるような姿勢で殴りかかってくる。
1本背負いの最高のタイミングだ。
ジョージ君は無我夢中でじゅうたんの上に彼女を投げ飛ばした。
ボーイフレンドはその間、震えながらただ見ているだけだった。
ジョージ君も興奮していた。
仰向けに転んでいる上半身裸の彼女の上に馬乗りになり、左右の手を押さえた。
さすがに、殴るわけにはいかない。
「マービン、PLEASE STOP、You can not beat me up. やめてくれ、君は俺には勝てない」
「どうして?チビのおまえに私が負けるはずがない」
ジョージ君は彼女を起こした。
立ちあがるなり、また左右のパンチを繰り出してきた。
懲りていないようだ。
ジョージ君は今度は両手でブロックした。
そしてまた右足で蹴ってきた。
それを予知していたジョージ君は再び体をかわし、思い切り彼女の足を払った。
ハイヒールはふっ飛んで、窓ガラスにあたった。
ガチャーンを大きな音はしたが、割れてはいないようだ。
彼女は大きく一回転し、もんどり打って倒れた。
床に強く体を打ちつけたようで、泣きだした。
ヤバい、これは大事件だ。
相手は女性、しかも高校生である。
ジョージ君にとってはすべて正当防衛であるが、雇用主の娘だ。
不安がよぎった。
やがてマービンは立ちあがり、子供のようなあどけない泣き面だった。
「私は一度も喧嘩で負けたことがなかった。お父さんもいないので強い男の人を知らない。ジョージは強いのね」と笑いだした。
負けて、気持ちがすっきりしたようだった。
しかし彼女が笑顔でも、安心はできない。
もうこの家を出ていかざるを得ないだろう。
そう覚悟をした。
キャサリンが帰ったらすべて正直に話して、この家を出よう。
正当防衛だし、警察に行ってもいいと思っていた。
ヒールは凶器で、ナイフと同じだ。
ジョージ君は、殺されるところだったと、言うつもりだった。
柔道のマーティンに叩きのめされて以来、絶対に避けてきた争いに、また首をつっ込んてしまった。
ここでホームステイをするどころか、下手をすると、これ以上アメリカに住めなくなるような大きな事件になる可能性もあった。
数日後、キャサリンが帰ってきた。
ジョージ君はすでに荷物をまとめていた。
すべてのいきさつを話し、「これでお別れしたい」と言った。
キャサリンはマービンを呼んだ。
マービンは何も言わなかった。
「ギャー」と言葉にならない野生の雄たけびをあげ、母親とジョージ君を睨みつけた。
キャサリンはジョージ君が心配するほど、大きな問題にしたくないようだった。
落ち着いた声で言った。
「マービン、あなたに出て行かれたら私は喧嘩相手がいなくなってしまうわ。さあ、機嫌をなおして、ここにいなさい。ジョージも、ここを出ても行くあてもないでしょう?」
確かにそうだった。
ジョージ君はだまって部屋に帰るしかなかった。

つづく