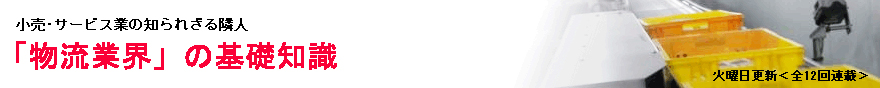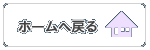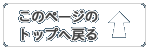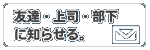vol. 08-1 輸送事業の中心を占める陸運業界
★鉄道に代わり自動車が国内輸送の主役に
前回に紹介したように物流、なかでも輸送の仕事は、
トラックなどの自動車、鉄道、船舶、航空機といった輸送機関が担っている。
ではそれぞれの輸送機関は、どの程度の勢力を占めているのだろうか?
わが国の国内輸送に限ると、
1年間に運ばれる荷物は、約54億トンといわれる(2007年、平成19年度)。
そのうちの49億トンは、トラックなど自動車輸送によるもので、
分担率でいうと、全体の9割超を自動車輸送に依存している。
自動車輸送に次いでは、
大きく差が開いて内航海運の4.1億トン(分担率7.6%)、
さらに差が開いて鉄道輸送の5100万トン(同0.9%)、
そして航空輸送の115万トン(同0.02%)が続く。
一方、輸送量を示すには、重量(トン)だけでなく、
「重量×輸送距離」の「輸送トンキロ」という指標がある。
つまり、「どれだけの量」を運んだかだけでなく、
それらを「どれだけの距離」運んだかも加味することで、
各輸送機関の本当の実力を示そうというものだ。
これでいうと、全体の年間輸送量は5800億トンキロ。
自動車輸送はそのうちの3550億トンキロ、分担率で6割超を占める。
次いで内航海運が2030億トンキロ(分担率34.9%)、
そして鉄道輸送230億トンキロ(同4.0%)、
航空輸送12億トンキロ(同0.2%)と続き、
分担率の順番は変わらないが、その割合は重量だけの場合とは異なり、
自動車以外の輸送機関も意外と健闘していることがわかる。
ちなみに輸送機関ごとの平均輸送距離は、
自動車に比べると鉄道が6.4倍、内航海運が6.9倍、
航空にいたっては14.5倍だ(いずれも2007年度)。
輸送量については、第二次大戦から5年後の1950(昭和25)年には、
重量で4億9000万トンと現在の11分の1の規模だった。
それが10年後には15億2500万トンと3倍強に増え、
高度経済成長時代を経て、60億トン近い現水準に拡大した後、
バブル経済でピーク(約68億トン)を迎えてから、緩やかに減少している。
もちろん多少のデコボコはあるものの、
輸送量の推移は、面白いほどにわが国の経済の実体を反映しており、
物流はまさに「経済動向を映す鏡のようなもの」だということがよくわかる。
1950年と2007年について、各輸送機関の分担率の推移を見ると、
目につくのは、鉄道輸送の退潮と、その反対に自動車輸送の躍進ぶりである。
鉄道が重量で26.9%から0.9%へ、
トンキロでも50.3%から4.0%へと分担率を落とす一方で、
自動車は重量で63.1%から91.4%へ、
トンキロでも8.7%から60.9%へと分担率を上げている。
このように、国内の貨物輸送の主役の座は、相変わらず陸運業界が占める。
ただしその中心は、高速道路網の整備などと軌を一にして、
1960年代から急速に進んだモータリゼーションなどの影響で、
鉄道輸送から自動車輸送へと移っているのである。
次回は、そうした主役交代の背景などについて、見ていくことにする。
(続きます)
〈by 二宮 護〉