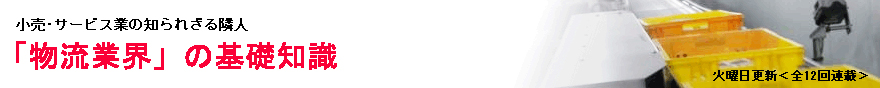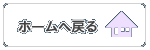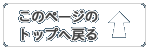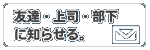vol. 02 物流は流通機能の一部を担う
★小売業や物流業は生産と消費の架け橋
今回は、物流の「機能」について紹介する。
「機能」というとややカタい感じを受けるかもしれないが、
物流が私たちに「何をしてくれているか」という本源的なことであり、
ぜひ押さえておいてほしいテーマの一つだといえる。
まず、少しだけ私たちの歴史を振り返ってほしい。
完全自給自足を実現できなかった人類は、物々交換の体制を経て、
必要なモノを経済活動によってまかなう社会をつくり上げたのはご存じのとおり。
その際、生産者と消費者に分業化することで、
そこに、①所有権、②距離、③時間という三つの隔たりが生まれた。
つまり、モノをつくる人と使う人、モノをつくる場所と使う場所、
そしてモノをつくったときと使うときのタイミング、
それぞれにズレが生じたのである。
そこで、これらのズレを埋め、
生産と消費をスムースに行うために登場したのが「流通」の機能だ。
なかでも「所有権の隔たり」には、
消費者と生産者や製造者との間に流通業者(卸売業や小売業など)が介在し、
取引(価格を決め、売買をして所有権を移転すること)を繰り返すという
「商的流通」(商流)という機能が隔たりを埋めた。
一方「距離の隔たり」には、生産地から消費地へ運ぶ「輸送」の機能が、
「時間の隔たり」には、生産されてから消費されるまで「保管」する機能が、
それぞれの隔たりを埋めた。
この「輸送」と「保管」の機能を担ったのが、
「物的流通(physical distribution)」(物流)の活動である。
このように、そもそも小売業と物流業は、お互いに協力しながら、
それぞれ流通の機能の一部を果たす“お隣さん”として生まれたことがわかる。
現在では、消費者に対してさまざまな商品を販売する小売業と、
それらの商品を着実に小売店頭に供給する物流業との協力関係は、
より広範で緊密なものになっているといえる。
まず、こうした協力関係は国内だけにとどまらなくなっている。
エネルギーの96%、食料の60%、基幹産業の原材料の90%は
国境を超えて運ばれてくるという統計もあるが、
小売業が海外に商品を求めることが増えているからだ。
さらにSPA(製造小売業)や大手小売業のPBなど、小売業の海外生産の進展や、
フードサービスが食材を海外に求めるなど、
経済のグローバル化が拡大していることも大きい。
こうして、小売業・サービス業と物流業界の協力関係は、
国内の、しかも流通段階の「販売物流」にとどまらず、
生産に先立って必要となる原材料や部品などを調達する「調達物流」、
生産現場において部品や製品を保管・管理する「生産物流」など、
さまざまな場面でより緊密に行われるようになっているのである。
(続きます)
〈by 二宮 護〉