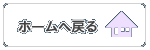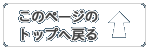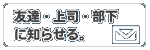スーパーマーケットのマーケティング Vol.35
35. 新プロセスモデルのフィードバック
●見切り発車後の中間チェック
試行錯誤的問題解決のむずかしさを乗り越えるための知恵の出し方を、事前準備→見切り発車→フィードバックの繰り返し→目的実現の4ステップに分け、第2ステップの見切り発車まで検討してきた。次は第3ステップの諸課題の掘り下げである。
すでに見てきたように、フィードバックの目的は一口にまとめれば、あいまいさを残したまま見切り発車した計画の妥当性を検証すること、および、あいまいさを順次より明確化することである。
妥当性の検証、あいまいさの明確化の過程で修正・調整ポイントがクローズアップしてくる。クローズアップした修正・調整課題は、次の計画の改善項目として反映される。
●近所のスーパーマーケットでの実例(その1)
あいまいさの明確化と改善項目のクローズアップにこんな関係があることを私自身が体験した。拙稿を記述しだしてから、散歩を兼ねて家の近くのスーパーマーケット2店で買い物をした。
1店では、数ヶ月前に青果売場に地元野菜コーナーを新設していた。新設当初は、改善を進めているなとは思ったが、何のための改善なのかは深く考えなかった。拙稿を書き出して、「おいしさに焦点をおいた改善」を意識しだしてから、このコーナーに差し掛かった時、ふと、おいしさとコーナーの関わりに何があるのかと考えた。とりたての野菜は鮮度がよい。鮮度の良い商品は味がよい。だからとりたての地元野菜のコーナーを設置した。この程度の理由づけはすぐできた。
しかし、コーナーを見ても、商品はちっともおいしそうに見えない。陳列が乱れ過ぎていて、品切れしたアイテムもあるからである。どうやらこのコーナーは契約農家が朝一回、商品を納入、陳列して、あとのフォロー作業はほとんどしないのではないかと想像された。これでは逆効果になる。これがその時の結論であった。
続けて、こんなことも考えた。例えば、トウモロコシなら畑で完熟したものを朝のうちに収穫し、その日のうちに食べれば、市場経由のトウモロコシにはない、おいしさを味わえる。完熟のおいしさである。「完熟」は野菜や果物のおいしさの1つの側面である。
山梨の釣りの帰り、地元の路面販売所で完熟した桃を土産に買って帰りたくなるような心理が分かったような気がした。
●近所のスーパーマーケットでの実例(その2)
もう1店の方では、次のようなことがあった。
このスーパーマーケットの鮮度管理の業務システムを作り上げて以来、地に足の着いた改革を着実に積み重ねている。いつ行っても売場が乱れているようなことはない。従業員はいつもにこやかにきびきび働いている。レジで待たされ過ぎたり、不愉快な思いをさせられたこともない。私の好きなスーパーマーケットの1つである。
1~2か月前、このスーパーマーケットに行った時、商品の吟味が行き届きだしたのに気がついた。陳列されている商品はすべてよく吟味されていることが分かった。百貨店に勝るとも劣ることのない吟味ぶりである。
もっとも百貨店のような高級品、高額品は省かれているが。スーパーマーケットのコンセプトに基づいた品揃えの商品吟味であろう。
デコポンは大きく色つやもよく、おいしそうに見える。トマトも、刺身も、ステーキもみんなおいしそうである。立派である。
●シアーズローバックの商品吟味
少し横道をそれるが、シアーズローバックの商品は吟味が行き届いていたという。
吟味法として注目すべき点は、商品の耐久性に主眼をおいたことである。試験室ですべての商品の耐久性をチェックした。チェックの方法は、商品にショックを与えて、いつまで壊れないかを確認した。その確認の方法が徹底していた。壊れるまでショックを与え続け、所要時間確認し、品揃えに入れる可否を判断したのである。
シアーズがこのような吟味を行うルーツは、カタログ販売にあったという。カタログ販売では、お客はカタログを見て商品を選び、メールオーダーして代金を払う。購入した商品が、例えばラジオがすぐに壊れたり、セーターが破れたり、変色したりしてもクレームのしようがない。テキサスのお客がシカゴの本社に商品交換や代金返済を要求することは、事実上できない。一度こんな目に遭わされたお客は二度と、カタログ販売の商品は買わなくなる。
こんなわけで、シアーズでは品質(耐久性)に焦点をあて、GMSにおいても、十全に行うようになったという。
●信頼のおける商品管理
アメリカのGMSとスーパーマーケットでは、取扱商品が全く違う。GMSの取扱商品はソフトグッズ(衣料品)とハードグッズ(家具など)であり、スーパーマーケットは食品である。
食品では耐久性は鮮度ではかられる。鮮度の客観的表示法は賞味期限である。生鮮食品は商品づくりした日の日付で表示されている。
かくしてスーパーマーケットは品質吟味のために賞味期限、日付管理の技法システムを作り上げた。
前記、私の挙げた2番目の店では、賞味期限、日付管理の技法は高次に定着している。
鮮度管理の目的は、安心・安全である。安心安全面では、このお店は全く信頼がおける。だから好きなのである。
続きます