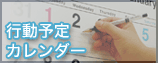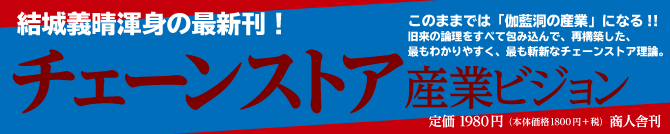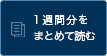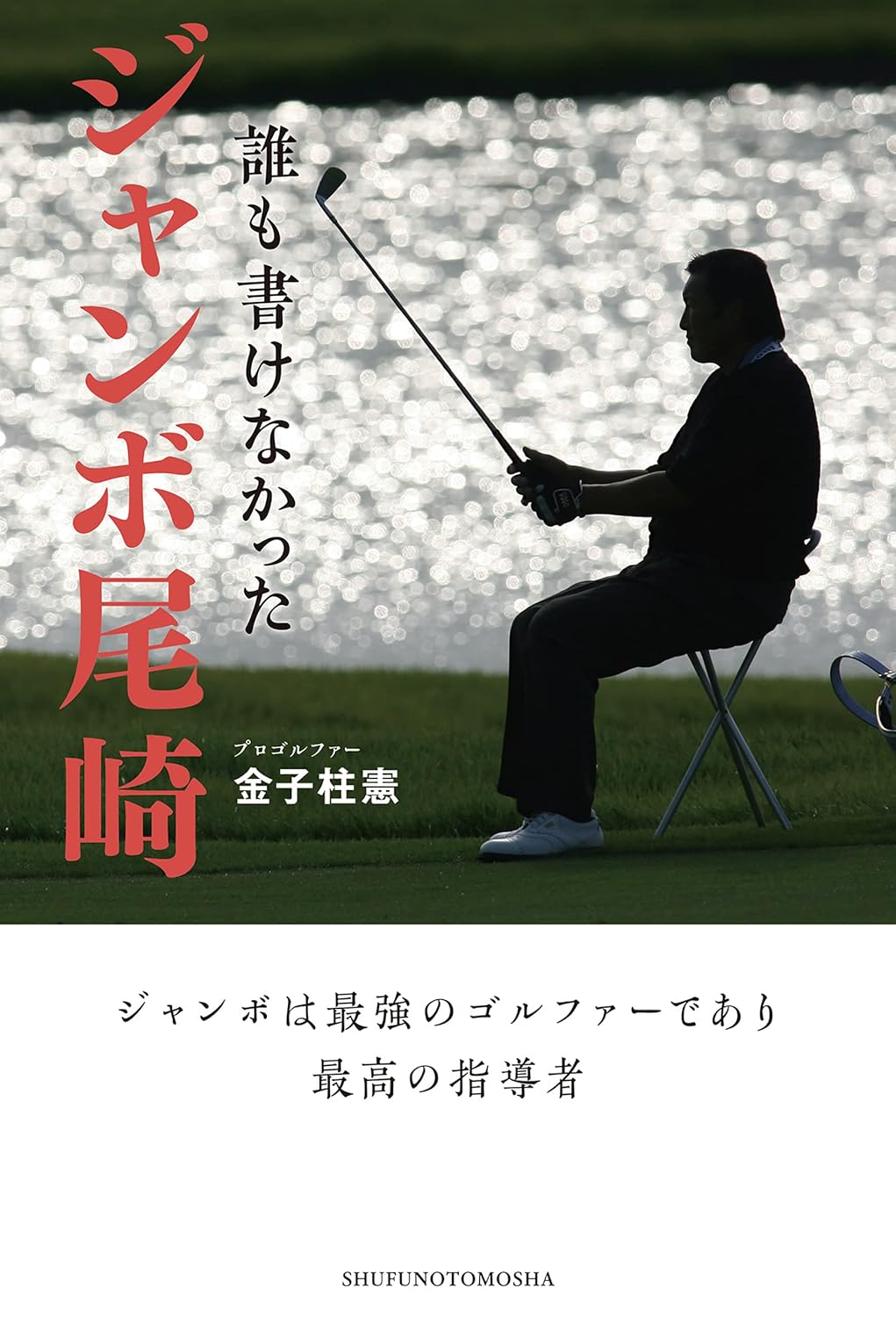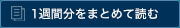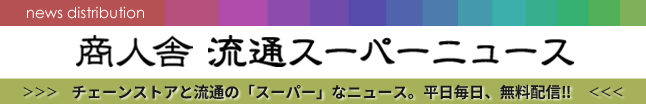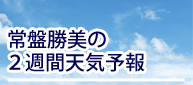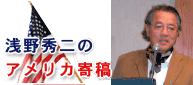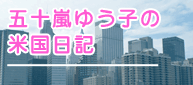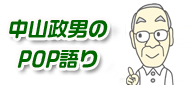訃報/ハローデイの加治敬通さん61歳、ジャンボ尾崎78歳、合掌。

クリスマスイブ。
だが訃報。
加治敬通(かじ・のりゆき)さんが亡くなった。
㈱ハローデイ代表取締役社長。
12月23日、61歳だった。
本当に残念だ。
経営者としては、
まだまだこれからという年齢だが、
加治さんは61年間を、
他の人の何倍ものスピードで、
駆け抜けたのだと思う。

通夜と葬儀告別式は家族葬で執り行われる。
そして後日、「お別れの会」が開かれる。
加治さんは、昭和39年(1964年)2月18日、
福岡県京都郡苅田町生まれ。
私の一回り下で辰年。
同じ福岡県生まれ。
そんなこともあって、
親しくした。
大学卒業後、父親の経営する家業に入った。
家業はスーパーマーケットだった。
父は故・加治久典さん。
久典さんも2014年4月6日、
癌性リンパ管症によって76歳で逝去。
加治さんは、平成元年1989年(平成元年)、
会社を背負うことを決意。
その時の会社の状態は、
年間売上高60億円で借入金60億円、
経常損失1億円の赤字だった。
金利は9.6%という状態だった。
毎年利子だけで5億7600万円。
そしてバブルが弾けた。
そこから2年間、1店舗の店長として、
死に物狂いで仕事に打ち込んだ。
学んだことはどんどん実行した。
失敗を恐れなかった。
1年後、その店だけで、
8000万円の純利益が出た。
嬉しかった。
会社にも、やればできるという、
自信のようなものが生まれた。
そして、こう考えるようになった。
「寝てもさめても新たな試み」
これが加治敬通の原点だ。
今、残された人たちは、
「寝ても覚めても新たな試み」で、
仕事に邁進してほしい。
その後、18期連続の増収増益を達成。
平成20年(2008年)に、
㈱ハローデイ代表取締役社長に就任した。
その2008年11月、
商人舎の第1回国内店舗視察研修会開催。

加治さんとハローデイに全面協力をいただいた。
バス2台をつらねて店を見て、
本部で加治さんの話を聞いた。

2009年6月16日には、
福岡県小倉の本社を訪問して対談した。
CDオーディオセミナー。

「三本の指事件」は印象的だった。
それを加治さんは手振り身振りで説明してくれた。

人を指差す時、人差し指は、
その人を指している。
しかし、三本の指、
すなわち中指、薬指、小指は、
自分を指している。
人を非難するとき、
その非難は自分に対して、
3倍になって向けられている。
加治さんの経営者としての生き方が、
「三本の指」に示されていた。
日本で一番見学者の多い会社となった。
そして加治さんは「日本一働きたい会社」を目指した。
2011年には私のコーディネートで、
一緒にアメリカを訪れた。 
一昨年2023年の9月には、
フードストアソリューションズフェアで、
対談した。
加治さんに1時間、経営を語ってもらった。
私はコーディネーターとして登壇。
コロナ下で加治さんが決断したのが、
チラシを止めるという「良い戦略」。
実によかった。

「寝ても覚めても新しい試み」の話、
ディスカウントストアとの闘いの話、
「三本指」の話。
いずれも謙虚な話しぶりだったが、
とても印象的だった。
ツーショットの写真。
これが最後となった。
もう会えない。
寂しい。
ご冥福を祈りたい。
この人もなくなった。
尾崎将司さん。
「ジャンボ尾崎」
1964年春のセンバツ甲子園優勝投手。
福岡の西鉄ライオンズに入団したが、
3年でプロゴルファーに転身。
その後、研鑽して、
ツアー通算94勝を含むプロ113勝。
12回の賞金王となった。
豪快なドライバーと、
繊細なショートゲーム。
勝負強さ。
派手なキャラクター。
日本のゴルフブームをつくった。
しかし海外では勝てなかった。
二人の弟もプロゴルファーになって、
「尾崎三兄弟」と言われた。
弟子たちを集めて、
「ジャンボ軍団」と呼ばれた。
引退後は、
ゴルフアカデミーを主宰して、
若手育成に情熱を注いだ。
特に女子プロは逸材を輩出。
笹生優香、西郷真央、原英莉花、
そして佐久間朱莉。
笹生は全米オープンを二度制覇、
西郷は今年のシェブロン選手権優勝、
佐久間も今年、日本の賞金女王。
育てることでも成功した。
ここが凄い。
2010年には青木功に次いで、
日本男子2人目の世界ゴルフ殿堂入りを果たす。
加治さんも尾崎さんも、
癌で亡くなった。
癌は人類の敵だ。
しかし二人ともやり遂げたことがあった。
それは多くの人々に感動をもたらした。
ありがとう。
合掌。
〈結城義晴〉