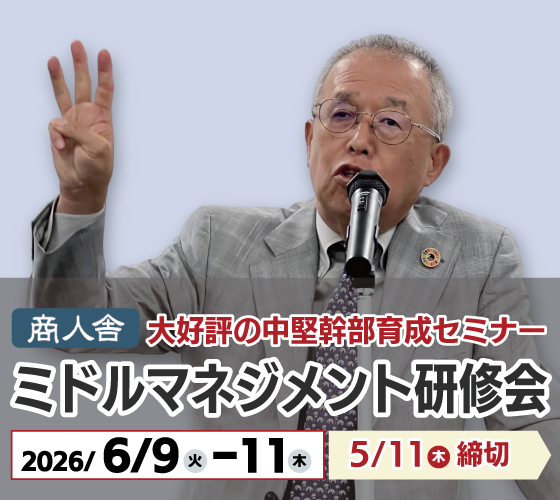食薬同源

臨床医・新居裕久が発表した「医食同源」とは、
病気を治療するのも日常の食事をするのも、
源は同じだという考え方だ。
中国最古の医学書『黄帝内経』に由来する。
「聖人は既病を治さず、未病を治す」。
ここから「食薬同源」の思想が生まれた。
病を治すのではなく、病を未然に防ぐ。
病を治す薬と日々の食事は源を同じくする。
健康を守る最良の方法は薬ではなく、食にある。
医学の父と異名をとるギリシャのヒポクラテス。
「汝の食事を薬とせよ、汝の薬は食事とせよ」
「食」が日々の予防医学そのものだった。
アメリカのドラッグストア産業は、
「セルフメディケーション」を重視する。
顧客が自分自身で薬事治療と食事療法をする。
中国とギリシャの古典的な医学も、
アメリカと日本の現代の消費産業も、
「食薬同源」と「医食同源」をコンセプトとする。
スーパーマーケットとドラッグストア。
それらがコンバインした「フード&ドラッグ」、
あるいは「ドラッグ&フード」。
食と薬の源は同じであり、
だから薬の小売業は食の領域に入ってきた。
必然のごとく薬と食の販売は結合してきた。
スーパーマーケット業態がそれを実現するのか、
ドラッグストア業態が先行するのか。
その競争はこれから本格化する。
しかし勝利するのは規模が大きな者ではない。
どれだけ人々の健康に貢献できるか。
その思想を全社で共有できるか。
たとえばタバコを販売し続けるのか。
それを中止することができるか。
人々の命と体を守るために。
売上げの3割をタバコに頼るコンビニは、
食薬同源の競争の舞台に乗りにくい。
置き去りにされざるを得ない。
勝利するのは規模の大きな者ではない。
真に人々の健康に貢献する者。
命と体を守ることができる者。
医食同源と食薬同源。
あなたはそれを推進できるか。
あなたはそれを自ら実践できるか。
〈結城義晴〉