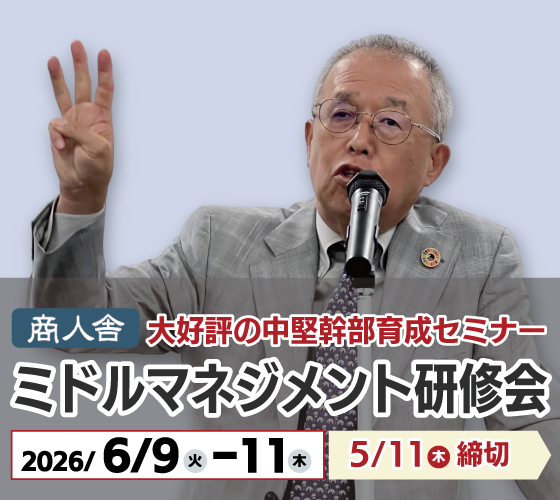復興は「祭りの神輿(みこし)」と「べらぼう」の「出版人の心意気」

17時3分、三陸沖を震源とする地震発生。
マグニチュード6.7。
岩手県、宮城県は震度4、
青森県や山形県、秋田県は震度3。
午後5時12分には、
岩手県の沿岸で津波注意報。
日本国は地震列島の上にある。
新潟日報の巻頭コラム「日報抄」
10月23日版。
「復興とは何ですか-。」
中学生に聞かれた、
上村靖司長岡技術科学大学教授。
答えた。
「復興とは、
複数の人が一つのものを担ぎ、
同じ方向に向かっていくこと」
上村教授がイメージしているのは、
「祭りの神輿(みこし)」
日本列島で私たちはいつも、
神輿を担いでいなければならない。
日経新聞「直言」
小説家の京極夏彦さん。
1963年北海道生まれ、62歳となった。
1994年『姑獲鳥の夏』でデビュー。
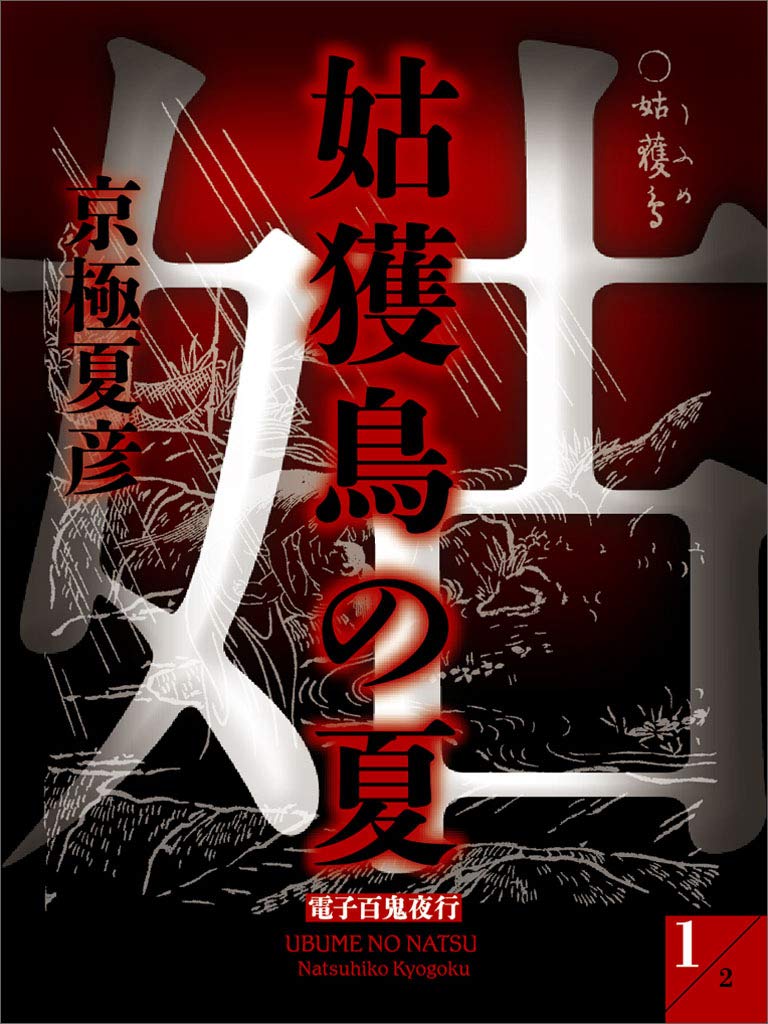
実に面白かった。
1996年に『魍魎の匣』で日本推理作家協会賞。
これも一気に読んだ。
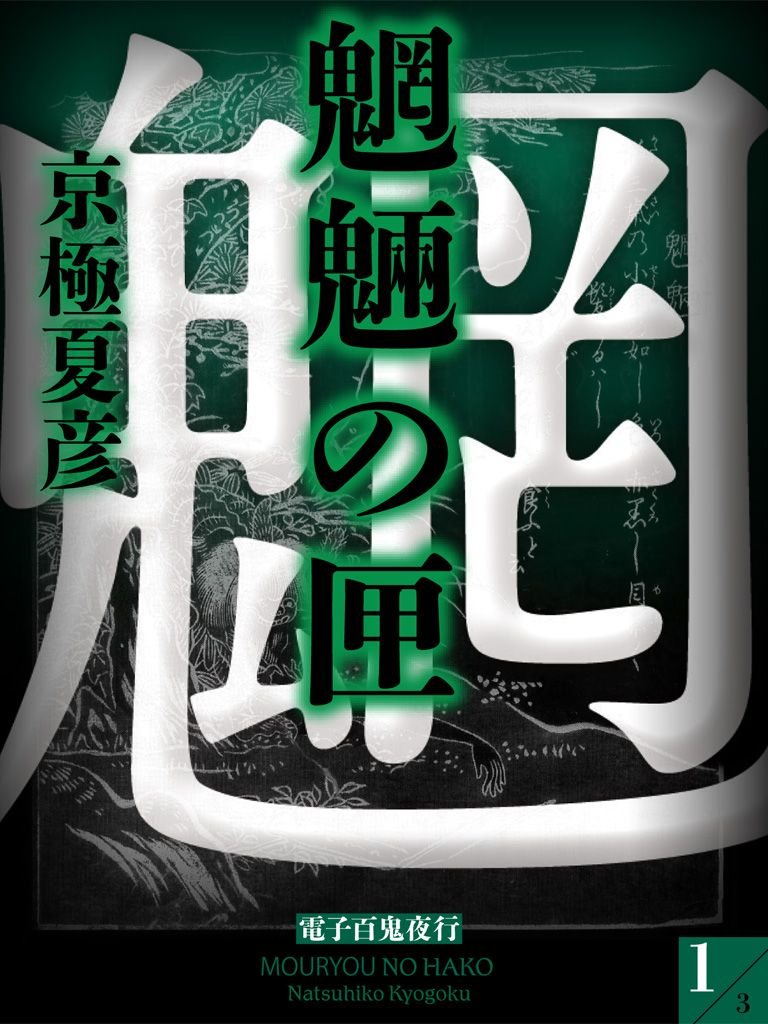
2004年に『後巷説百物語』で直木賞。
2025年4月から印刷博物館館長。
賛同したい。
「よきたたずまいの本を作ることが、
ないがしろにされている」
「本は安い文庫ばかりが売れるわけではない。
手の込んだ装丁のハードカバーを、
好む読者も確実にいる」
出版不況と言われている。しかし、
「不況ではない。
業界の構造的な欠陥なんだと思う」
同感だ。
「1980年代、高額の書籍が消費者に忌避され、
代わりに安い書籍の点数が増えた。
本の主力商品はハードカバーから文庫へと移った」
私も商業界の編集担当取締役時代、
新書シリーズなどをつくらせようとした。
「今は、放送ですら
オールドメディアと言われるような世の中。
紙にインクをつけて本にするなんて、
古いと思われて当然かもしれない」
「その陰で忘れられていることがある。
印刷はあまりの美しさに
『芸術』とまで呼ばれるものを
生み出せる技でもある」
「実際、グーテンベルクが
大量印刷の機械を作った500年前は
魔術とさえ言われたものだ」
凄い発明だった。
私もよく、講演で使うネタだ。
「本作りの目的は、
ムダをなくすことではない」
「本作りとはムダを排除するのではなく、
むしろ取り込んでいくものではないか」
京極夏彦は、
本づくりにこだわる。
「(本をぱっと開いた時の)版面が、
読者にとってどのように見えるのかは、
すべて僕ら書き手の責任だと思う」
雑誌も同じだ。
「読者が目にするのは印刷された最終製品。
途中でいくら一生懸命やったって、
製品にそれが表れていなかったら全然ダメだ」
「紙の印刷ってすごいことができるんだと、
見せつけるような製品を作ろう。
そんな気持ちで自分は仕事をしてきた」
いいことです。
「効率優先で本が作られ、
デジタル空間にもひと目見ただけでは
区別がつかないフェイクとファクトが並ぶ」
「玉石混交の状況は、
プロの出版人の意識次第で変わりうる」
その通りだ。
私たち商人舎もそうありたい。
「印刷の歴史は、
社会の動向にほぼ寄り添って進んできた。
こうあってほしいという時代の要請に応じて、
行き過ぎることも遅れることもなく技術ができてきた」
「電子書籍やインターネットといった電子メディアも、
そもそも印刷という発想がなければ
今の形にはなっていない」
「何とか記録を残したいという
願いをかなえる技術、
つまりは複製技術の延長線上に
メディアというものはある」
「次世代のメディアも当然
この流れを受け継いで出てくる」
「印刷技術を古いものと捉えるのは
表層的に過ぎる」
だから私は紙(magazine)と、
網(ウェブサイト)を融合させたい。
そして紙はいつも必要だ。
「みんなが書き手になり、
玄人と素人が同じ土俵に立っている。
そんな中、文章の内容はもちろんのこと、
装丁やレイアウトといった見た目の面でも
さすが玄人だね、と言われる作品を
つくり出さないといけない」
「デジタルは画面の拡大や縮小ができる良さがある。
ただ、そうした時に字組みが崩れる。
版面というものの意識がすでに変容しているが、
対応するような作品はいまだない」
「僕も書こうかと思ったが、
技術的に難しかった。
時代が要請していないのか」
「いや、みんなが事の重大さに
気づいていないだけなのかもしれない」
京極夏彦は「本」と「印刷」のことを言っている。
しかし本も雑誌も同じように、
印刷によって成り立っている。
いい本、いい雑誌。
美しい本、美しい雑誌。
私たちもつくりたい。
NHK大河ドラマ「べらぼう」。
つい見てしまうのは、
その出版人の心意気を共感したいからだ。

倉本長治は蔦谷重三郎の評論を書いた。
日本で一番早い蔦重論だった。
倉本初夫も蔦重研究者だった。
デジタルにはないものの良さ。
今、私たちも求め続けたい。
〈結城義晴〉