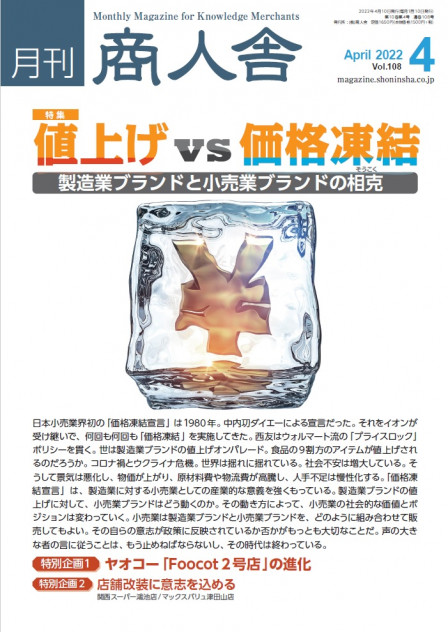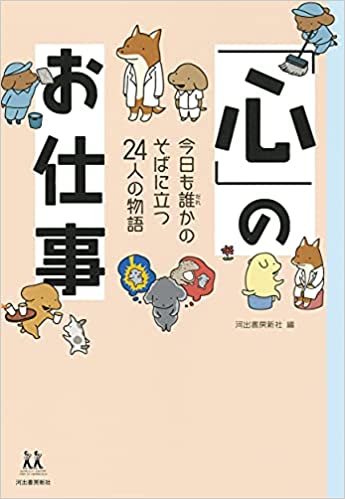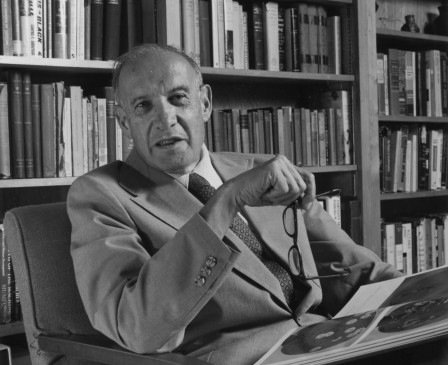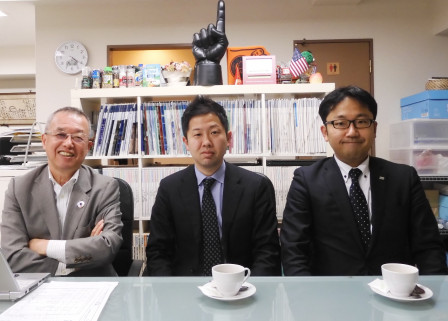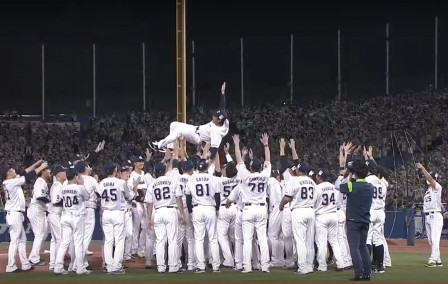10月1日。
2022年も、
きっちりあと3カ月。
訃報が続く。
アントニオ猪木。
プロレスラー、
79歳で逝去。
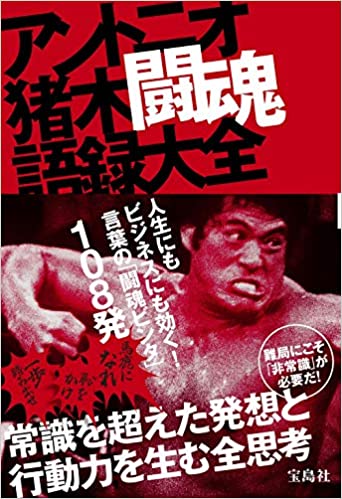
伝説的な日本のプロレスラーは、
力道山、
ジャイアント馬場、
アントニオ猪木。
たとえは適切でないかもしれないけれど、
哲学の世界の、
ソクラテス、
プラトン、
アリストテレス、か。
力道山は大相撲の力士からの転身で、
日本プロレスを創設。
1963年、39歳で没した。
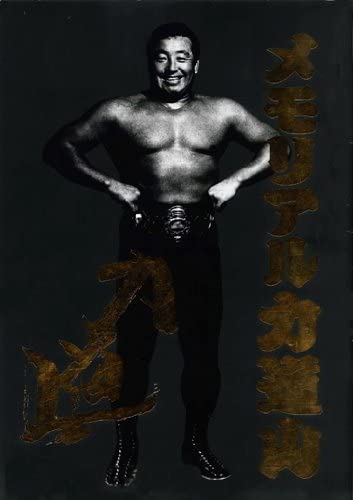
馬場はプロ野球の巨人軍から、
力道山の日本プロレスに移籍して、
その後継者となった。
1999年、61歳で亡くなった。
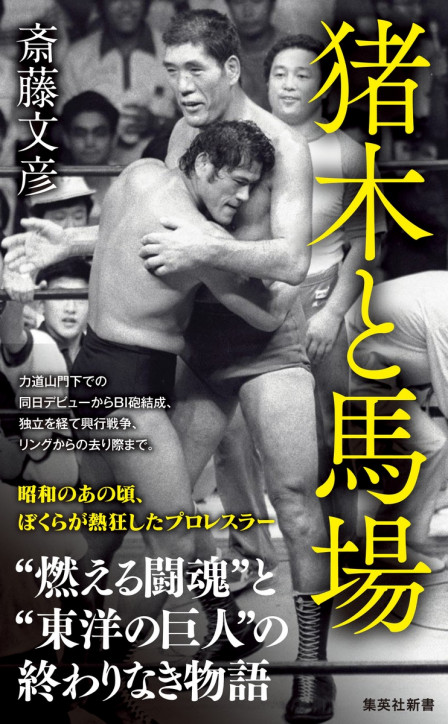
猪木寛至(かんじ)は、
力道山にブラジルでスカウトされて、
17歳でプロレスラーとなった。
その後、「燃える闘魂」と称され、
「ストロングスタイル」を標榜した。
コブラツイストや卍固め、
アリキックや延髄切りなど、
派手な技を売り物にしたが、
バックドロップや、
腕挫(うでひしぎ)十字固めなど、
オーソドックスな技こそ、
群を抜いて巧かった。
また異種格闘技戦を敢行して、
イノベーションを志向した。
対戦相手は、
柔道のウィレム・ルスカ、
空手のウィリー・ウィリアムス、
ボクシングのモハメド・アリなどなど。
猪木のあとは「鶴藤長天」の時代を迎える。
馬場の弟子のジャンボ鶴田と天龍源一郎、
猪木が育てた藤波辰巳、長州力。
さらにタイガーマスクとして、
佐山聡が人気を博した。
大仁田厚は「デスマッチ」で、
興行的な成功を収め、
「インディー団体」が乱立した。
猪木の新日本プロレスには闘魂三銃士が登場。
蝶野正洋、武藤敬司、橋本真也。
馬場の全日本ではプロレス四天王が台頭。
三沢光晴、川田利明、田上明、小橋健太。
彼らは例外なく猪木をモデルにした。
馬場ではなかった。
猪木は現役を引退してから、
参議院議員なども務めたが、
最後は病魔と闘った。
心臓の難病「全身性アミロイドーシス」
そして燃え尽きた。
超のつく肉体的ハードワークに耐え、
79歳まで生きた。
それは実に立派だった。
ご冥福を祈りたい。
さて10月は、
食品値上げラッシュの月だ。
10月の1カ月間で値上げされる食品は、
6699品目に及ぶ。
帝国データバンクの9月末の調査。
今年の値上げの3分の1が10月に集中した。
年間では2万665品目の値上げである。
便乗値上げがないことを信じたいし、
それを祈りたい。
アメリカではステルス値上げが、
顧客に見破られて、
逆作用を示した。
つまり余計に売れなくなった。
イオン㈱の発祥の㈱岡田屋の「家訓」。
「上げで儲けるな、
下げで儲けよ」
景気や相場などが上げ潮の時に、
みんなと同じように儲けるのではなく、
それが下がっている時に、
知恵を出して、儲けを捻出せよ。
こんな時だからこそ、頭を使う。
考えて考えて、考え抜く。
そして顧客が喜ぶ商売を生み出す。
大変化のときには、必ず、
それができる機会が潜んでいる。
しかし同時に10月から、
さらに激しい競争が待っている。
もう一度読み直して、
10月に成果を上げてほしい。
[Message of April]
カットスロートコンペティションへ。
争うこと。
競うこと。
闘うこと。
生死を分けること。
コロナパンデミックが往って、
ポストコロナの時代がやってくる。
競争のあり様は変わる。
強い者同士のより厳しい競争となる。
カットスロートコンペティションは、
喉を掻き切る競争。
激しくて途切れない競争。
消耗と革新の連続。
「戦争における行動は、
重たい液体の中で運動するようなもの。
ただ前進することも水中では、
敏捷、正確には行えない」
(クラウゼヴィッツ『戦争論』)
プロイセン王国の軍人クラウゼヴィッツは、
ロシアに侵攻したナポレオン軍が消耗し、
敗退するさまを目の当たりにした。
そして「戦争論」にまとめた。
戦場で軍の動きを拘束し、
その計画を台無しにするもの。
予想外の偶然や事故の連鎖を、
クラウゼヴィッツは「摩擦」と呼んだ。
会社の経営や店の運営も、
「重たい液体の中の運動」になることがある。
すると敏捷さと正確さが失われる。
それが「摩擦」であり、摩擦が生まれると負ける。
カットスロートコンペティションでは、
強敵ばかりの少数の闘いが展開される。
それは「重たい液体の中の運動」に似る。
その覚悟をし、腹を決めた者だけが生き残る。
カットスロートコンペティションでは、
現実を正確に認め、
夢を計画化した者だけが勝ち残る。
分析力と創造力、行動力だけが味方である。
ただし激しい競争であっても、
カットスロートコンペティションは、
戦争ではないし、殺し合いではない。
正々堂々の腕と知恵の競い合いである。
だからかならず、
それに参画する者にご利益がもたらされる。
勝利した者にも惨敗した者にも、
成長の証を示してくれる。
ただし、そこから逃走した者には、
大きな罰が下される。
参画しなかった者には、
なんのご利益も与えられない。
コロナパンデミックが往って、
ポストコロナの時代がやってくる。
競争のあり様は変わる。
強い者同士のより厳しい競争となる。

アントニオ猪木も、
喉を掻き切る競争に明け暮れた、
ヒーローだった。
合掌。
〈結城義晴〉