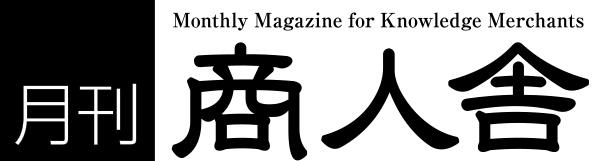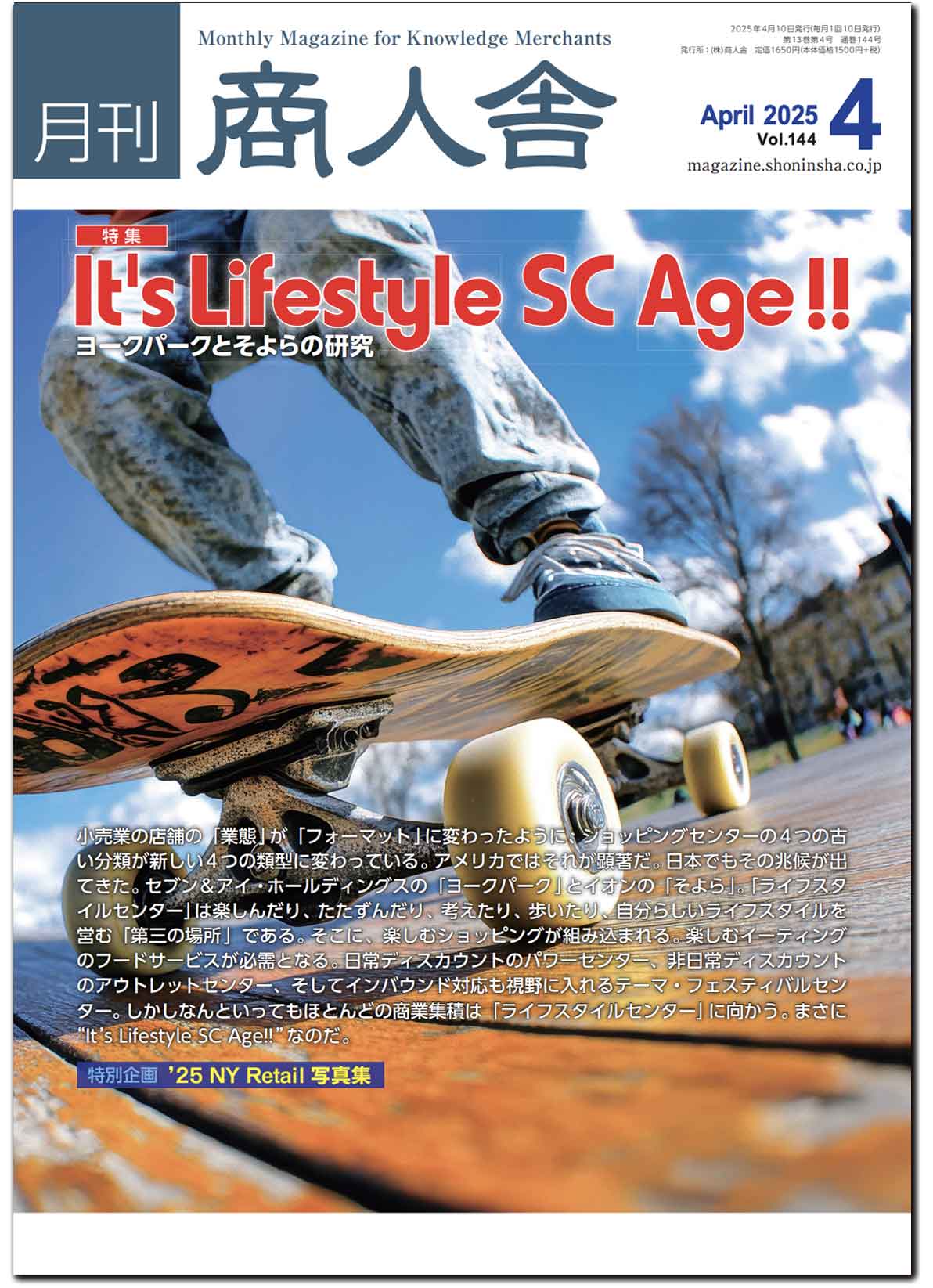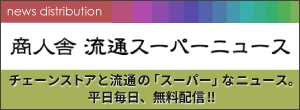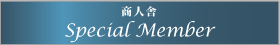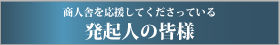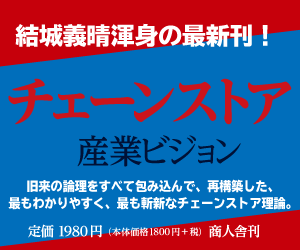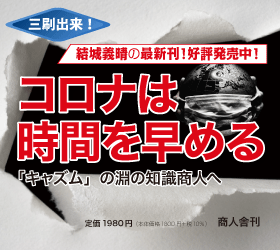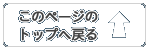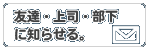将棋の第36期竜王戦。
七番勝負の第4局。
2日間のタイトル戦。
場所は北海道小樽市、銀鱗荘。
竜王・名人であるだけでなく、
王位・棋王・王将・棋聖・王座・叡王をもつ。
21歳。
タイトル戦以外にも、
一般棋戦と呼ばれる全棋士参加の棋戦がある。
こちらは持ち時間が少ない。
テレビのNHK杯や銀河戦、
朝日杯、JT日本シリーズ。
この4タイトルも昨年度は、
藤井が全部獲得してしまった。
今、将棋界のすべてのタイトルは、
藤井がもっている。
その藤井に同年の伊藤匠七段が挑戦した。
今、最高位とされる竜王戦。
1988年までは十段戦と呼ばれた。
それを読売新聞が「竜王戦」と改め、
賞金を棋界最高にした。
そこで竜王位が、
将棋界最高のタイトルとなった。
棋士たちも将棋界も、
金には弱い。
しかし私は、
名人戦こそ最高だと考えている。
棋士たちもそう考えているに違いない。
何しろ名人は江戸時代から続く。
徳川時代には名人は家元制だった。
つまり「終身名人」という地位だった。
1603年(慶長8年)、
征夷大将軍となった徳川家康が、
幕府を創設し、幕藩体制を構築した。
家康は将棋や囲碁にも力を注いで、
その組織体系をつくった。
1612年(慶長17年)、
家康は初代大橋宗桂に、
将棋の名人位を授けて、
俸禄を与えた。
その後、300年以上も、
終身制が続いた。
明治、大正、昭和となって、
1937年(昭和12年)、
十三世名人の関根金次郎が、
自ら名人位を退位し、
実力名人制が始まった。

関根は阪田三吉をライバルとした。
第1期名人戦は、
木村義雄が初代名人となった。
藤井聡太は第十八世名人である。
竜王戦とは歴史が違う。
重みが違う。
ただし現在は、
賞金トップの竜王と歴史ある名人は、
ほぼ同格であると見ていい。
藤井聡太はその竜王戦の防衛戦に臨んだ。
そして見事に挑戦者の伊藤匠七段を破った。
2日制タイトル戦としては、
驚くほどの早指しで、
初日が終わった。
そして伊藤が封じ手を行った。
そのまえに、
やや不利な形勢にあった藤井は、
飛車で角をとるという、
2四飛の勝負手を指した。
飛車のほうが角よりも価値は高い。
その次は、
誰が見ても同歩と飛車をとるしかない。
その、誰が指してもこれしかないという手を、
伊藤は封じ手にした。
巧みだ。
伊藤は100%、同歩しか指さない。
そうすると藤井もまた100%、
次の手は3二角成りしか指さない。
そうすれば一晩、伊藤は、
3二角成りの次の展開を、
自分だけが考えることができる。
夜が明けて9時、
やはり伊藤は2四同歩を指し、
藤井は3二角成りを指した。
ここでAIによる評価で、
伊藤が6割ほどの優位に立った。
しかし一晩考えに考えたその次の手が、
なんと敗着となってしまった。
6七銀打ちである。
藤井聡太は、
不利な体勢にも拘わらす、
その後のすべての手を読み切っていた。
最後の最後は37手詰め。
芸術的な詰将棋のごとき手順で、
勝ち切った。
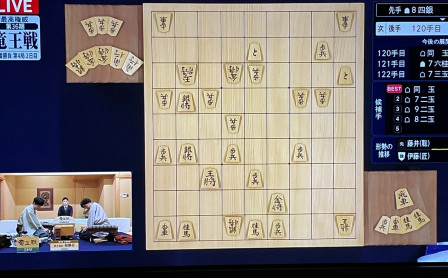
ヒヤリとする手を連発して、
最後は自分の持ち駒がゼロになった。
完璧な詰将棋の如き終幕。
間違いなく今年度の「名局賞」になる棋譜である。
藤井は美しい棋譜を残したいと考えている。
それを竜王戦最終局で創り上げてしまった。
終局後の藤井のコメント。
「本局は中盤で苦しくしてしまったいましが、
その後は受けに回って、
チャンスを待つ展開にできました」

これでタイトル戦は19戦無敗。
故大山康晴十五世名人が、
タイトル戦連勝記録をもつが、
それに並んだ。
伊藤匠。
現在、永瀬拓也と並んで、
最高のAIによる研究者だ。
対局が終わって感想戦。
立会人は渡辺明九段と広瀬章人八段。
渡辺は前名人・元竜王、広瀬も元竜王。
藤井聡汰の言葉。
「将棋を指す限り勝敗はついてまわるので、
一喜一憂してもしょうがない」
成功や失敗に一喜一憂してもしかたない。
一喜一憂は無駄である。
仕事も商売も同じだ。
「“派手な手“と“地味だけど最善手”の兼ね合いは、
とても難しいと思います」
商売にも派手な手がある。
地味な最善手もある。
ともすると派手な手を打ちたがる。
それも不要ではないが、
地味な最善手が何より求められる。
「手順には芸術的な美しさがあります」
この芸術的な美しさは、
売場づくりにも店づくりにも当てはまる。
ちなみに第4局の会場は、
北海道小樽市の料亭・温泉旅館「銀鱗荘」。
所有者は(株)ニトリパブリック。
銀鱗荘は1939年の創業。
もとは積丹半島の大網元の屋敷「鰊(ニシン)御殿」
現在の小樽・地平磯岬へ移築して、
高級旅館になった。
北海道文化財百選。
(株)ニトリホールディングスが、
2018年8月に取得した。
それもあって、
似鳥昭雄会長の長男の似鳥靖季総支配人が、
藤井竜王に記念品を手渡した。
派手な手と、
地味な最善手。
将棋にも商売にも両方必要だが、
私は地味な最善手が好きだ。
〈結城義晴〉