結城義晴「ギリギリ主義・コツコツ主義」と丸山眞男「精神の惑溺」

暑いあつい8月末の土曜日。
横浜の最高気温は36℃。
午後から車で商人舎オフィスに出社。
やっぱり原稿執筆には、
ここが一番いい。
着いたらすぐに、
熱い珈琲を淹れる。
いや淹れてもらう。
商人舎オフィスの豆は、
問屋から直接、買ってくる。
酸味が強いのが好きだ。
月刊商人舎9月号の原稿執筆と編集業務。
月曜日から9月。
学校の新学期が始まる。
私は子どものころから、
なぜかギリギリ主義だった。
どうしてだろう。
父も母も何でも着々と進めるタイプだった。
妹もコツコツ宿題をやっていた。
私だけギリギリまで先延ばしにした。
小学生、中学生、高校生。
だからいつもこの時期は宿題に勤しんでいた。
高校3年の時だけは夏休みの宿題はなかった。
大学受験の時期だったからだと思う。
なんだか嬉しかった。
社会人になると、
どういうわけか、
毎月〆切のある仕事に就いた。
それ以来、もう50年近くになる。
ビル・ゲイツもギリギリ主義で、
「これが一番能率が上がる」と言っている。
さらに商人舎を設立する直前から、
毎日〆切のある生活になった。
このブログを始めたからだ。
私は神を信じる者ではない。
けれど運命のようなものは、
ご都合主義で持ち出してくる。
ウォルマート創業者のサム・ウォルトンの言葉。
“Retail is Detail”などは、
「小売りの神は細部に宿る」と訳したりする。
そんな風に神がいるとしたら、
結城義晴のような怠け者には、
〆切を与えねばならないと決めたのだろう。
子どものころからギリギリ主義でも、
一日いちにち、〆切が来れば、
それは日々のコツコツ主義になる。
うまくできている。
それにも感謝しておこう。
さて、朝日新聞「折々のことば」
編著者の鷲田清一さんには、
本当に感謝している。
第3467回。
自由と専制との
抵抗闘争関係そのもののうちに
自由があるのであって、
自由の単一支配は
もはや自由ではない。
(丸山眞男)
「明治の思想家・福沢諭吉が、
生涯説き続けたことの一つが、
価値の多元的存立が自由の基盤をなす
ということだった」
「たえず変化する状況の中で、
各人が一つの価値規準に呑(の)み込まれ、
主体的な判断を放棄する、
そんな精神の『惑溺(わくでき)』から
社会の停滞が起こる」
丸山眞男らしい。
あえて「惑溺」という言葉を使った。
「耽溺(たんでき)」と言う言葉もある。
惑溺も耽溺も、
「あることに夢中になり、
それ以外考えられなくなること」
「耽」は一つの物事に熱中することだが、
「惑」は正しい判断ができなくなること。
だから「惑溺」には、
心を奪われて判断力を失うというニュアンスがある。
正しい判断ができなくなるほど、
一つの価値基準に吞み込まれてしまう。
多くの人がそうなると、
社会は停滞する。
だから丸山は言う。
「自由は“多事争論”の中で育つ」
専制主義やポピュリズムは、
そこが危うい。
昨日の玉置泰さんの「人間発見」で、
伊丹十三さんが亡くなったあと、
宮本信子さんが詩を教えてくれる。
三好達治の「涙をぬぐって働こう」
とてもいい。
みんなで希望をとりもどして
涙をぬぐって働こう
忘れがたい悲しみは
忘れがたいままにしておこう
苦しい心は苦しいままに
けれどもその心を
今日は一たび寛(くつろ)ごう
みんなで元気をとりもどして
涙をぬぐって働こう
あんまりいい感じのしない世の中でも、
お客さんに喜んでもらう。
商売はとても明るい。
みんなでげんきをとりもどして、
涙をぬぐって働きたい。
〈結城義晴〉


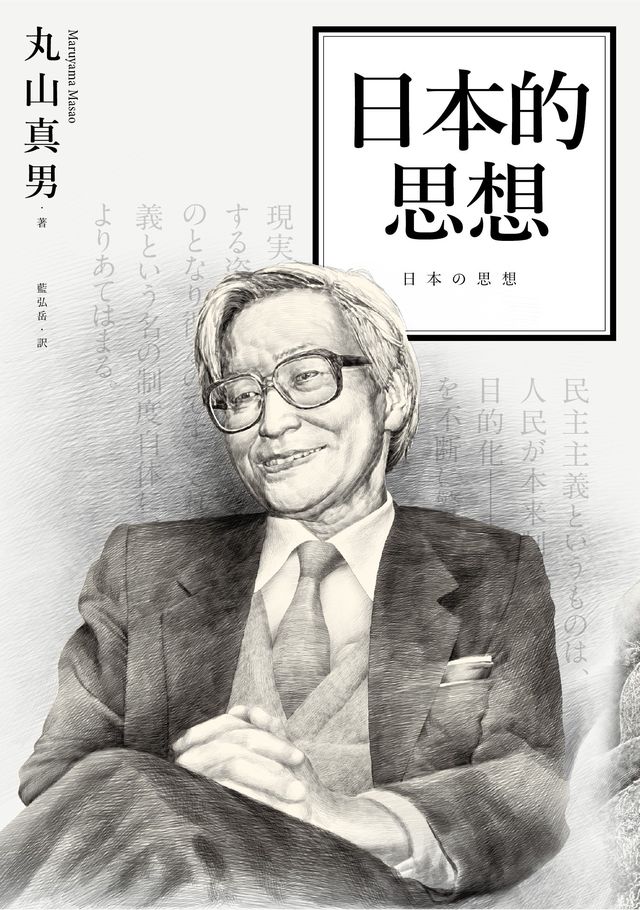
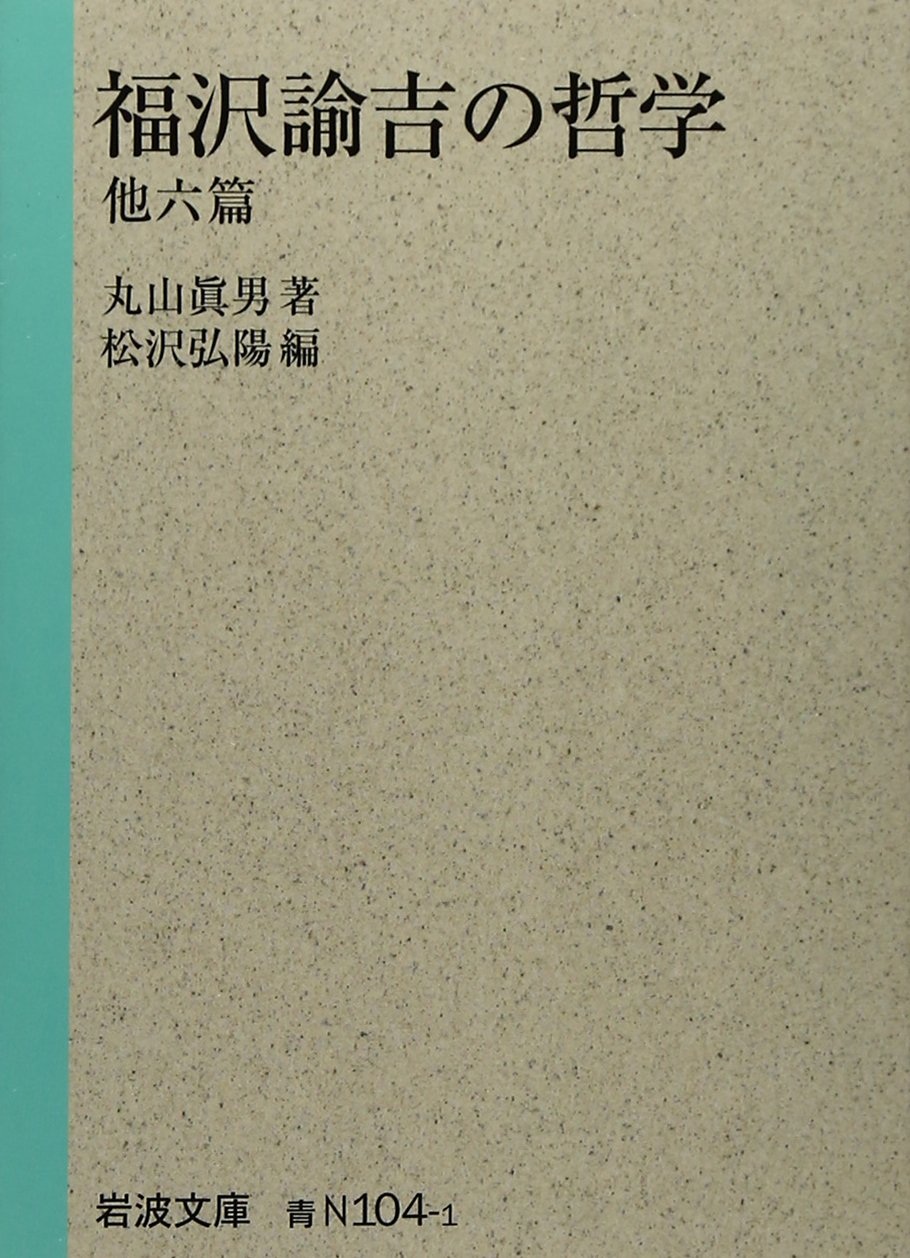





























2 件のコメント
私は、とりあえずすぐ着手する主義です。
一旦、少しでも着手してみることで、全体の見通しが立ち、落ち着いた気持ちで取り組めるからです。
色んな流儀があって面白いです。
吉本さん、いい流儀ですね。
うらやましい。