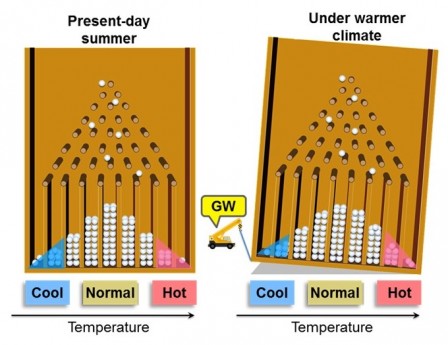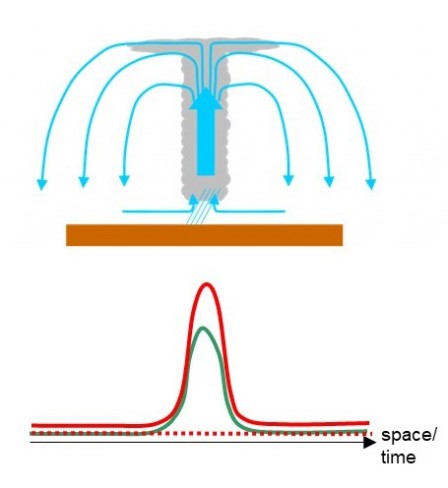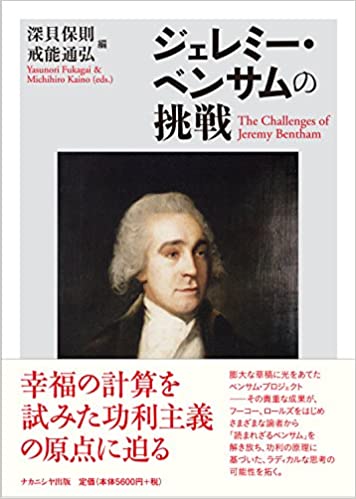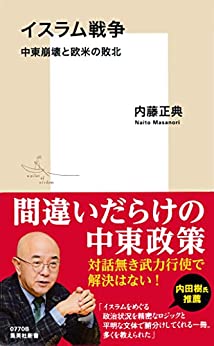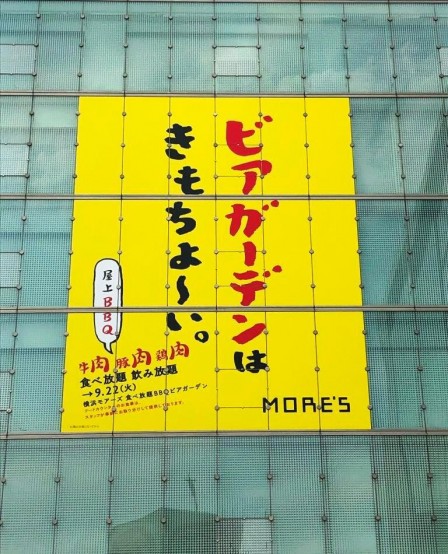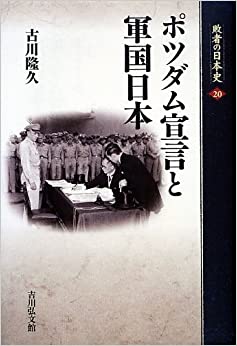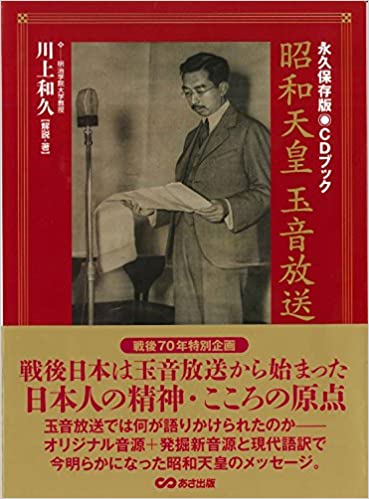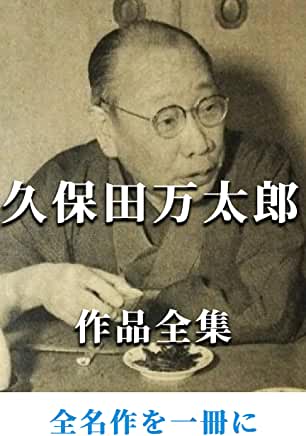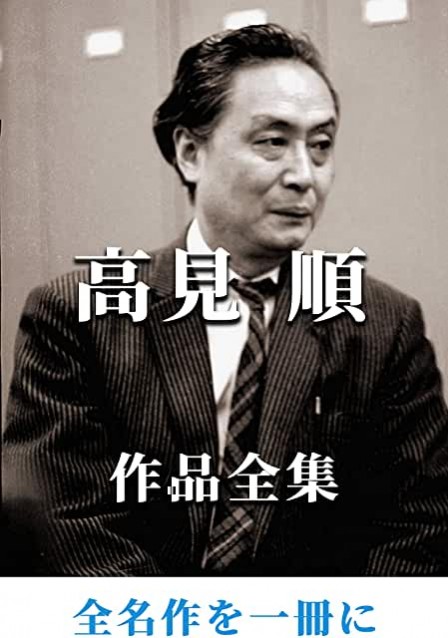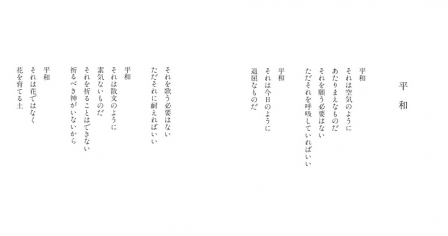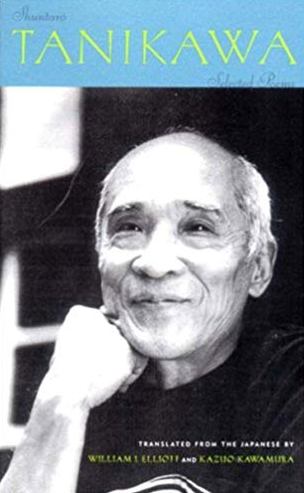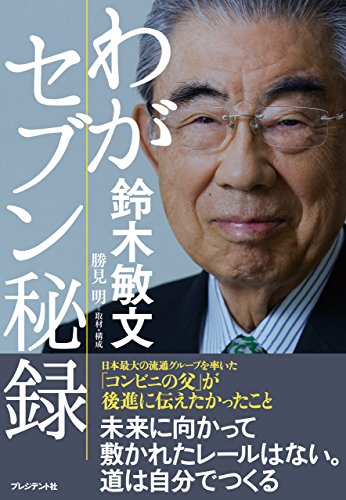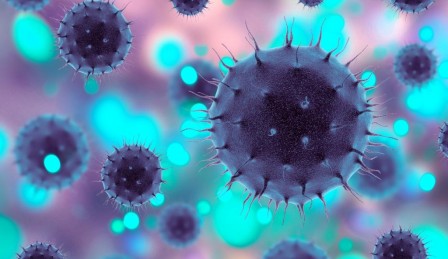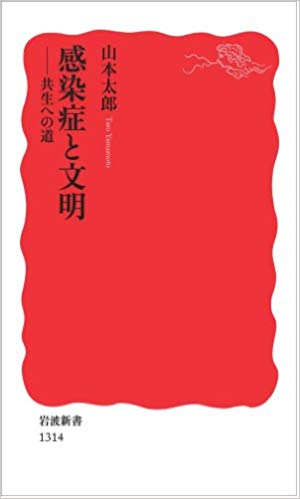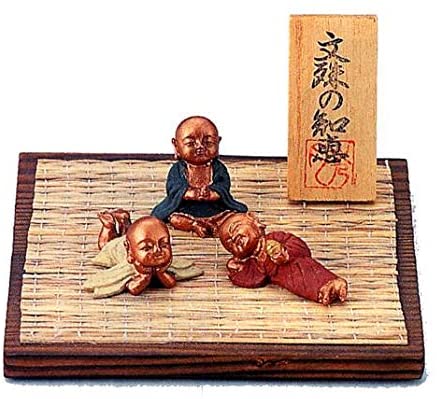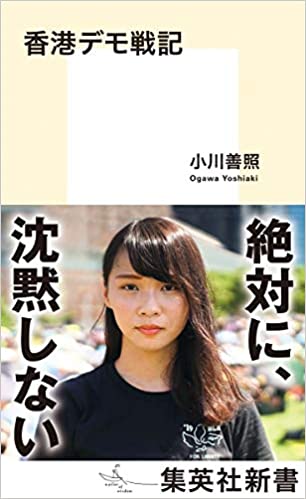大阪の最高気温は36.7℃。
横浜は33.8℃。
その大阪から横浜に来客。
私の隣から前田仁さん、小阪裕介さん、
稲越大樹さん、森川泰弘さん。
前田さんは万代ドライデイリー会事務局長。
小阪さんは㈱JTB大阪第三事業部営業四課長。
森川さんは同グループリーダー。
そして稲越さんは、
㈱万代総務部付業務サポートチームシニアリーダー。
今年から来年、再来年までの、
さまざまな事業やイベントのご提案。
私と商人舎にとっては、
このコロナ禍で懸案だった問題が、
どんどんクリアになって方向性が見えた。
前田さんの力量を思い知らされたし、
「前田チーム」の仕事のスピード感も実感した。
コロナは時間を早める。
心から感謝したい。
ランチは野田岩横浜店で、
天然鰻を堪能した。

さて[商人舎流通SuperNews]
PPIHnews|
年商1兆6819億円26.6%増・経常10.2%増/ヤマダ抜いて第5位
PPIHは旧ドンキホーテホールディングス。
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス。
その2020年6月期本決算。
売上高は1兆6819億円、
前年同期比26.6%増。
これでヤマダ電機を抜いて第5位。
ヤマダの2020年3月期決算は、
売上高が1兆6115億円、
前年同期比0.7%増。
1位イオンが8兆6042億円(1.0%増)、
2位セブン&アイが6兆4436億円(2.2%減)
3位ファーストリテイリング2兆2905億円。
昨年8月期決算で前年比7.5%増。
4位アマゾン・ジャパンで1兆7444億円。
年平均為替レート換算で前年比14.3%増。
以上は月刊商人舎8月号より。
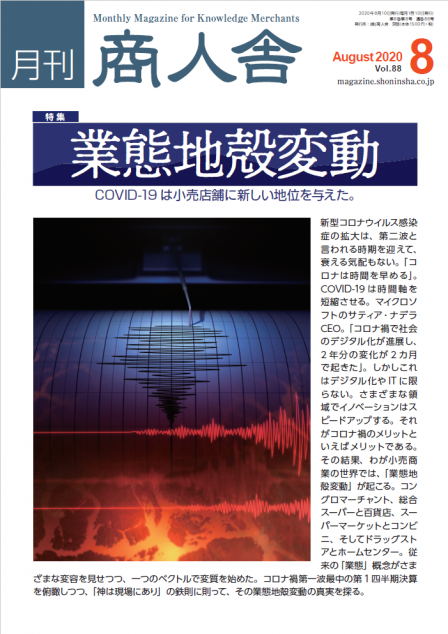
このアマゾン・ジャパンの次に、
PPIHが食い込んだ。
ユニーが昨2019年1月から、
PPIHの連結子会社となった。
だから総合スーパー事業の売上高は、
84.8%増の4916億円となった。
PPIHの営業利益は760億円(20.4%増)、
経常利益が752億円(10.2%増)、
そして当期純利益が503億円(6.9%)。
ヤマダの営業利益は383億円(37.5%増)、
経常利益461億円(24.9%増)、
当期純利益246億円(67.5%増)。
どちらも大幅増益だが、
営業利益はPPIHがヤマダのほぼ2倍。
PPIHは営業利益率、経常利益率ともに4.5%、
ヤマダは営業利益率2.4%、経常利益率2.9%。
業態は全く違うが、
2兆円に近い会社の利益率の2倍差は、
なかなか追いつけるものではない。
一方、3位のファーストリテイリングは、
2020年8月期通期見込みだが、
売上収益が1兆9900億円、
コロナ禍の影響で前期比13.1%減、
営業利益は1300億円で49.5%減、
当期利益は850億円で47.7%減。
4位のアマゾン・ジャパンが、
コロナ禍の影響で絶好調だから、
2021年度はまた地殻変動が起こるだろう。
6位ヤマダの次は百貨店が続く。
7位の三越伊勢丹ホールディングスは、
1兆1192億円。
8位は高島屋の9191億円。
9位はエイチ・ツー・オーリテイリングで、
8973億円。
Jフロントリテイリングは、
国際会計基準に変えたため、
売上高は4806億円で30位だが、
従来の営業収益換算で1兆1337億円、
日本の百貨店第一となる。
これは月刊商人舎6月号で指摘している。

来年の決算では、
コロナ禍の大打撃を受けて、
百貨店はすべて1兆円を割るだろう。
ランキングの変動だけでなく、
営業や組織、財務においても、
大きな変革を求められるに違いない。
最後に日経新聞電子版、
「経営者ブログ」
㈱IIJ会長の鈴木幸一さん。

この電子版が創刊されて10年が過ぎる。
その発足以来毎週連載ブログを書いて、
一度も休んだことがなかった。
それが先週の火曜日、お盆休みで休載。
心配したメールがどっと寄せられた。
私の[毎日更新宣言ブログ]は、
おかげさまで13年間、
1日も休んでいない。
ほんとうに「おかげさまで」。
その鈴木さん、
暑い中、エリック・ヴュイヤールを読む。
1968年、フランス・リヨン生まれの、
ハンサムな52歳の作家、映画監督。
この6月発刊のその著『その日の予定』
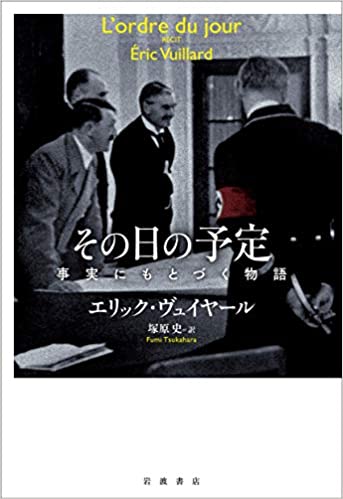
本の宣伝文句。
「第二次大戦前夜、
オーストリア併合に至る舞台裏を、
事実の断片から描き出す。
大企業家とナチ高官との秘密会合、
オーストリア首相を恫喝するヒトラー、
チェンバレンを煙に巻くリッベントロープ…。
彼らの卑小で時に荒唐無稽な行動・決断が
世界を破局に引き込んでゆく。
事実に基づく物語。
仏ゴンクール賞(2017)受賞作」
私も早速、購入した。
鈴木さんの引用部分。
「けれども、企業は
男たちと一緒に死ぬわけではない」
「企業とは決して死滅することのない
神話的な身体なのだ」
「オペル・ブランドは、
自転車を売り続け、
次に自動車を販売した。
創業者が死んだ時、
会社の従業員はすでに1500人を数え、
その数も増え続けた」

1862年に創業したオペルは、
1929年に米国GMの100%子会社となり、
2017年には仏グループPSAに買収される。
「企業は
一つの人格であり、
その身体の
すべての血液は
頭に上がっていく」
「それは法人と呼ばれ、
その生命は私たちの生命より、
はるかに永続する」
PPIH、ヤマダ電機、
そしてファーストリテイリング。
イオンとセブン&アイ。
さらにトップの百貨店群。
「企業は一つの人格であり、
その体のすべての血液は、
頭に上がっていく」
これは事実だ。
しかし企業が、
神話的な身体かどうか、
そうなれるかどうかは、
わからない。
多分、創業者の、
Will(意志)とIntegrity(真摯さ)が、
大きな比重を占めるのだろう。
〈結城義晴〉