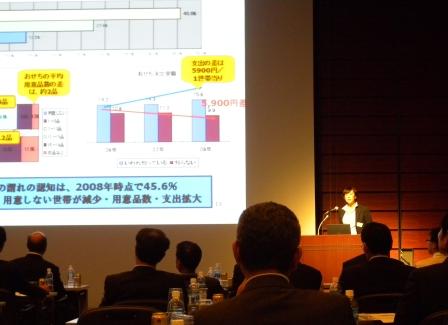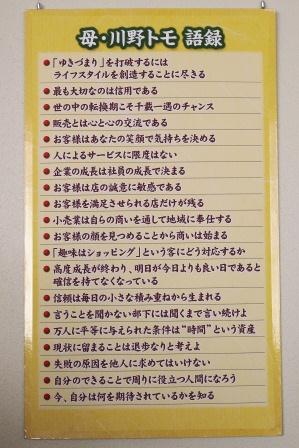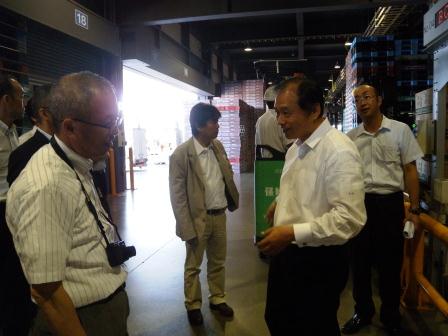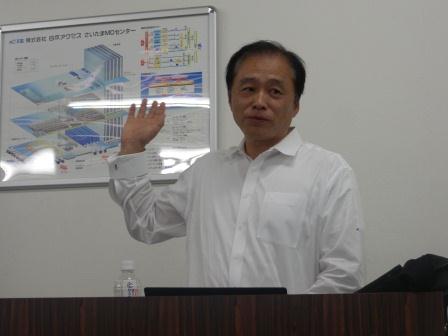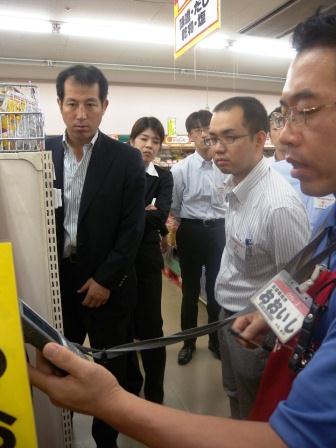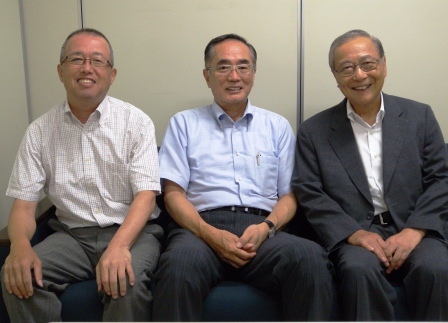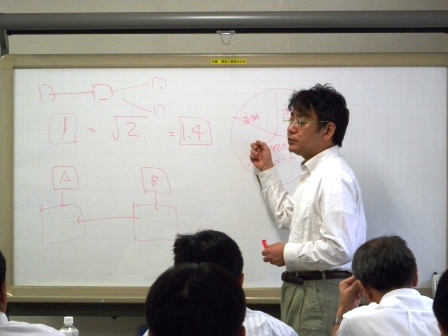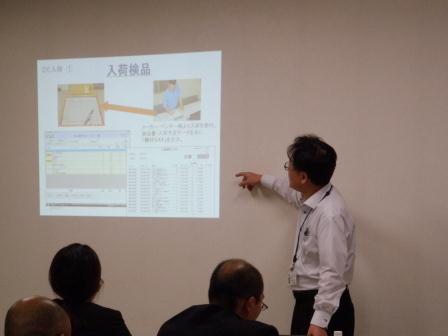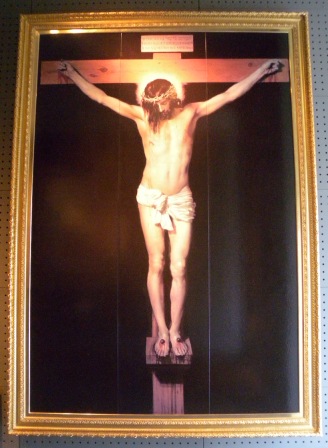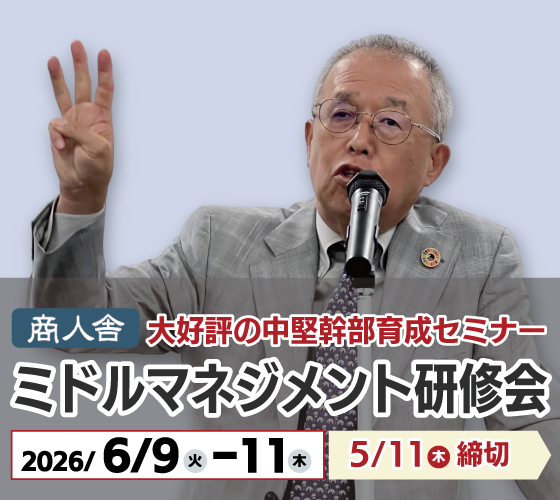良いニュースを二つ。
朝日新聞から、
「福島産早場米すべて出荷可能」。
福島県の調査結果の発表。
8月下旬から早場米の調査を始め、
20市町村の水田で計101サンプルを調べた。
いずれも国の基準値を下回った。
国の基準とは、
1キロあたり500ベクレル。
最後に県内4市町で収穫した早場米を検査、
国の基準値を超える放射性セシウムは、
検出されなかった。
これによって、
福島県内で収穫した早場米は、
すべて出荷が可能になった。
おめでとう。
もう一つはイオンの取り組み。
こちらは日経新聞。
「岩手・久慈で水揚げのサンマを全量買い取り」
イオンが提携したのは岩手県の久慈市漁業協同組合。
久慈市の漁港に水揚げされる北海道沖でとれたサンマは、
イオンによって全量、買い取られ、
東北・関東にあるグループ店舗で販売される。
目的は、大震災で被災した現地の漁業関係者の復興支援。
もちろん商売上もイオンには大きなメリットが生まれる。
第1は鮮度。
これらのサンマの店着は、
東北の店舗には水揚げの翌日、
関東の店舗には翌々日。
通常の市場仕入のサンマに比べると、
それぞれ1日早い。
第1回の水揚げは来週はじめの予定。
1回の水揚げ量は20~50トン、計7~8回。
10月中旬までに最大計400トンを買い取ることになる。
鮮魚として販売できない規格のサンマは、
現地業者がすり身に加工し、これもイオンが買い取る。
イオンは、宮城県石巻市の工場で生産したサンマのかば焼きなども、
プライベートブランドとして発売する。
当然ながら、全量買い取りが前提。
東日本大震災への支援をしつつ、
それが売る側、買う側両者のメリットにつながる。
近江商人の「三方良し」。
売り手良し、買い手良し、世間良し。
これです。
さて、日経新聞の大きな記事。
「味の素、ウォルマートに販路」
味の素は、この9月から米国のウォルマート本体と取引を始めた。
これによって全米約2500店舗で冷凍食品4アイテムが販売される。
今月末、私はテキサス州とカリフォルニア州を訪れる。
都市にすれば、ダラス、サンフランシスコ、サクラメント。
ウォルマートを見る楽しみが一つ、増えた。

ウォルマートで販売するのは、味の素の米国ブランド「サムライ」。
その鶏肉チャーハンとあんかけかた焼きそば、さらに「ミールキット」。
特にミールキットは、
「オレンジチキン」など米国定番メニューと米飯とを組み合わせた簡便商品。
各商品の容量は、1.15キログラム。
ウォルマートの定番に多い1箱3~4人分相当。
売価に関して、日経の記事では、
「店頭想定価格は9ドル前後となる見込み」とあるが、
おそらく8ドル98セントといった価格ポイントで、
リーチインケースでエブリデーロープライスで販売されるはず。

製品はオレゴン州の現地法人工場、
または中国・江蘇省の子会社工場で生産されている。
味の素全体の冷凍食品部門の売上高は、
2010年度で1095億円。
その海外比率は、数%。
ウォルマートとの取引を機に、
これを10%以上に拡大する計画。
このうちアメリカでの売上高は約65億円。
しかし米ドルベー スで年率1~2割の成長。
これを3年のうちに、100億円に乗せる。
そのためにまず、ウォルマートの店頭を押さえ、
次にクローガーやセーフウェイ、パブリックス、HEB、
そしてコストコ、ターゲットといった企業にもアプローチをかける。
米国でのアジア・エスニック風冷凍食品の市場は、
約800億円と試算される。
ここに日本食や中華料理、タイやベトナムのメニューが含まれる。
特にトレーダー・ジョーの売り場など見ているとわかるが、
この分野の成長率は年間5%の伸び率。
その理由は、アジア系・ヒスパニック系の住民の急増。
米国2010年国勢調査によると、
この10年間で、アジア系、ヒスパニック系ともに、
43%の増加。
日本人は増えてはいないが。
そしてアジア系、ヒスパニック系は、
日本食を大いに好む。
ウォルマートもそこに目をつけたということだ。
日本のメーカーは一部を除いて、
ウォルマートへの拒否反応が強い。
納入原価の買い叩きに遭うのではないか、
そんな被害妄想のようなところもある。
しかし丸裸の原価(ネットネットプライス)での取引は要求されるが、
いざ店頭に並んだら、当初の計画通りの売上げを達成する。
もちろんメーカーの利益も計画通りに生み出される確率が高い。
日本水産の垣添直也社長はそのことを述懐する。
ニッスイはアメリカに子会社の水産会社を持っていて、
その取引相手にはウォルマートとマクドナルドがある。
垣添さんは両社との取引に、
「計画通り」というメリットを見出している。
今回の味の素のウォルマートとの取引開始は、
日本の食品製造業が、
新しい戦略局面に入ったことを示していると思う。
日本独自の発達をし、
日本市場への最適化に専念してきたメーカー各社が、
国際化を目指そうとしている。
もちろんキッコーマンや伊藤園といった先行事例はあった。
その列に味の素が加わり、ウォルマートと取引を始めた。
国内空洞化と国際化との狭間の緊張の中で、
新しい局面が展開され始めた。
私は今日、明日と、
立教大学新座キャンパスで、
結城ゼミの合宿。
充実した時間を、
ゼミ生とともに過ごす。
ウォルマート店頭の「サムライ」ブランドとの対面を楽しみにしながら。
皆さんも、良い週末を。
今週も、結城義晴の[毎日更新宣言]、
ご愛読、感謝します。
<結城義晴>