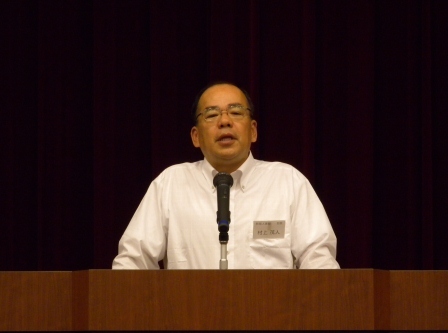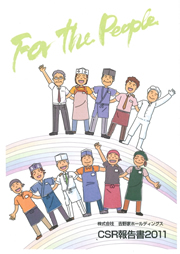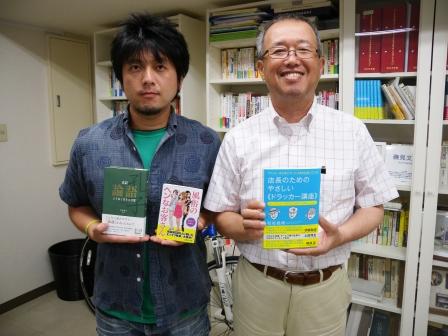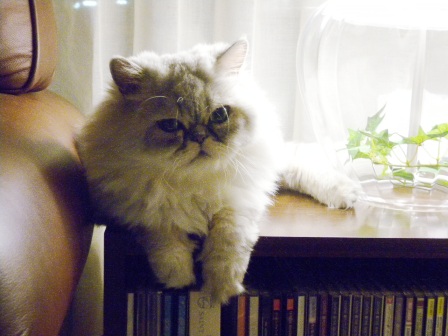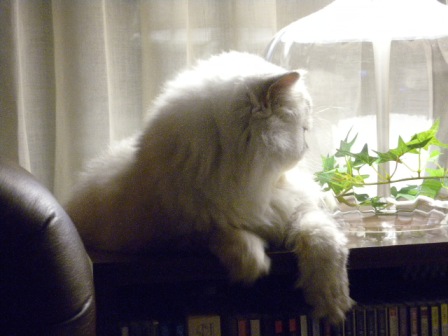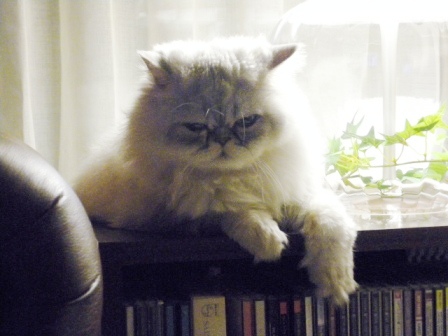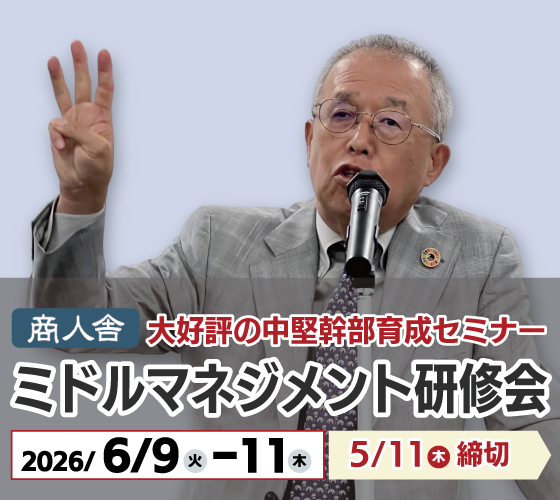前原誠司vs海江田万里。
反小沢vs親小沢、
あるいは脱小沢vs寄小沢?
今日告示の民主党代表選挙。
構図ははっきりしてきた。
良いか悪いか、
国会のため、国民のためには、
たぶん良いとは断定できないけれど。
日経新聞の「きょうのことば」が面白い。
「民主党グループ」を説明している。
「有力議員を中心とした集まり」で、
「最大勢力は約130人とされる小沢一郎元代表のグループ。
約50人の前原誠司前外相、菅直人首相のグループがそれに次ぐ規模」
「民主党グループは自民党の派閥のような結びつきは薄く、締め付けも緩いため、
大学の『サークル』にたとえられる」
大学サークルもいまや一人が最低3つくらいに属している。
民主党も複数のグループに参加する議員が多い。
だから「代表選では掛け持ち議員の奪い合い」が始まる。
それが極まるのが、今日明日、そして明後日早朝まで。
しかし、菅直人首相の退任は、
あんなにゆっくりしていたのに、
重要な次の首相の選任は、
こんなに急ぐ。
なんだか、まったく逆じゃないか?
世の中、逆のことって、
結構、多いけれど。
社員が現場で働かず、
役員が日々の業務に勤しむふりをする。
社員が会社の将来を無責任に語り、
役員は目の前の利益にあくせくする。
これ、歴史があるけれど、
体質が古い会社の典型的な構図。
そんな会社の役員になったら、
「最悪を覚悟して、
最善を尽くせ」
いつもこの心構えしかない。
そして少なくとも、
将来のビジョンや本来の理念を、
説き続けるリーダーであってほしい。
そのビジョンや理念が欠落していれば、
話にはならないけれど。
万が一、そんなことが起こっているとすれば、
いつでもご相談に乗る用意はある。
さてニューヨークには、
アイリーンがやってくる。
大西洋を北上中のハリケーン。
今夜あたりから、米北東部一帯を直撃する恐れが高まる。
7州が「非常事態宣言」。
ニューヨーク市ブルームバーグ市長は住民約30万人に対して、
史上初めて強制避難命令を出した。
地下鉄・バスの運行は全面停止される。
沿岸部の200人以上にも避難命令が出された。
アイリーンの規模は「カテゴリー2」。
5段階の下から2番目。
2005年の「カトリーナ」はカテゴリー3で、
約1800人が死亡。
しかしカトリーナはミシシッピ川沿岸の中南部だった。
アイリーンは人口密集地の北東部。
バラク・オバマ大統領は、
「歴史的な暴風雨となる」と警告を発し、
米軍は10万人態勢での出動を指令した。
さて、これも日経新聞の「まちかど」。
タイトルは、「『西高東低』に裏付け」
ただしここでいう「西高東低」は株式市場の株価の話。
「関西私鉄大手の京阪電と近鉄は今週、年初来高値を更新、
関東大手の東武や京成に差をつけている」
さらに百貨店も、
「近鉄百の株価も堅調で、日経平均が直近高値をつけた」
「騰落率は松屋や三越伊勢丹を上回る」
数字の裏付けがある。
「7月の百貨店売上高は、
マイナスだった東京に対して
大阪はプラス」
「6月の鉱工業生産指数も関西が関東を上回る」
一昨日から昨日まで、その関西に出張。
梅田駅上の三越伊勢丹は、
12階フロアの飲食店はごった返していたが、
それ以外の物販フロアは「買われていない」。
人は集まるが、買い物はしない。
この傾向。
しかしそれでも、全体でみると、
関東よりもいいようだ。
大阪のおばちゃんの言う「見てきた⤴?」
これ。
それでも、なんというか、関西は元気。
高速道路も混んでいた。
関西の積乱雲は、元気に見えた。

入道雲は、まだまだ盛り。

「脱小沢vs寄小沢」の対立構造鮮明化、
ニューヨークにはアイリーンが到来、
日本の株価・営業は「西高東低」
関東よりも、盛り上がっている。

昨日は朝から豊中の㈱阪食本部へ。
松元努常務(私の右)と志水孝行さん(左)と、
来年の研修会の打ち合わせのあと「疋田」で食事。
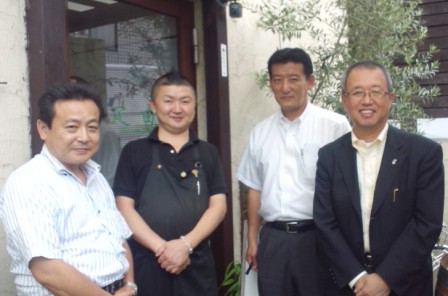
千野和利社長も登場くださって、
熱い熱いミッションを語り合った。
千野さんや松元さん、志水さんと会って話していると、
「西高東低」も理解できるような気がする。
<結城義晴>