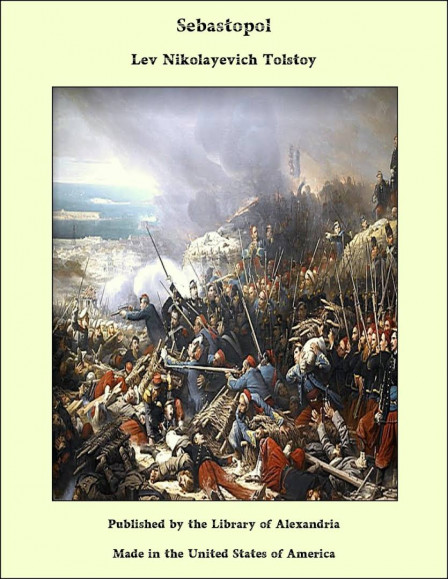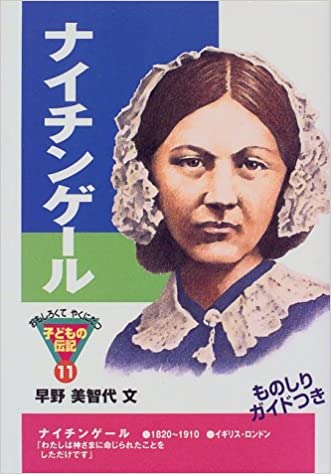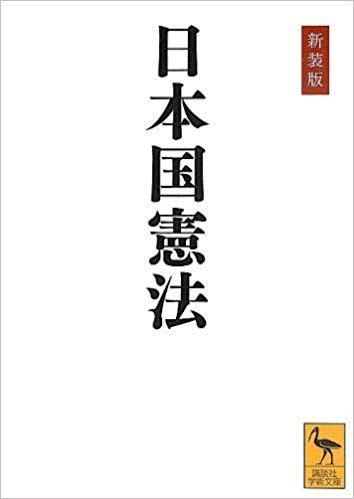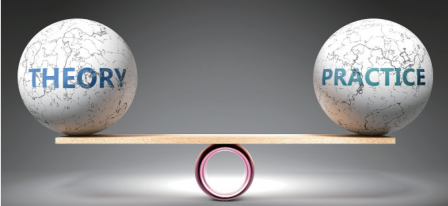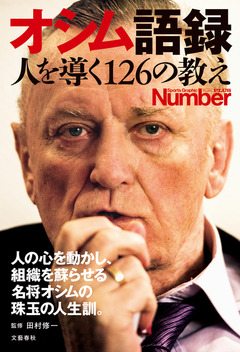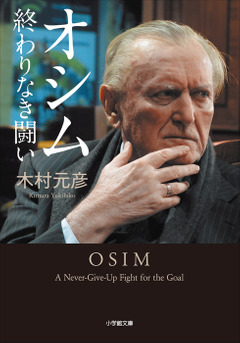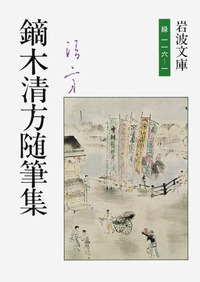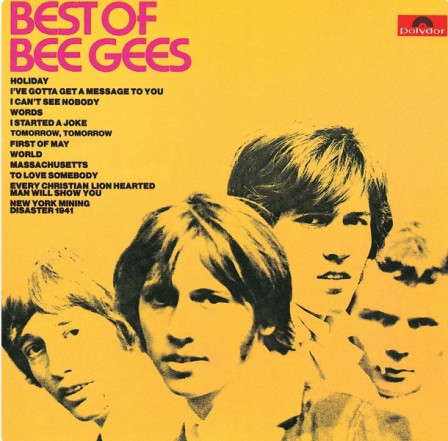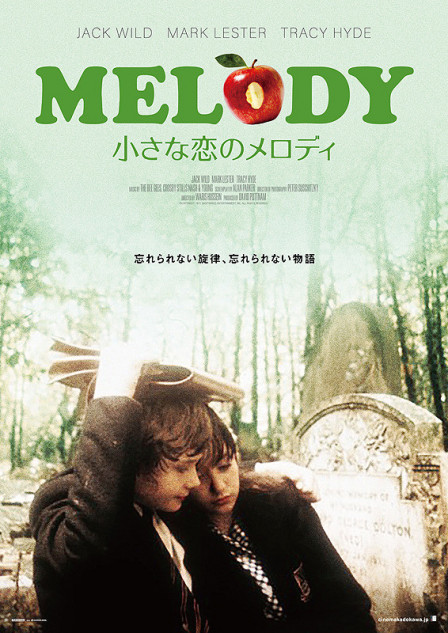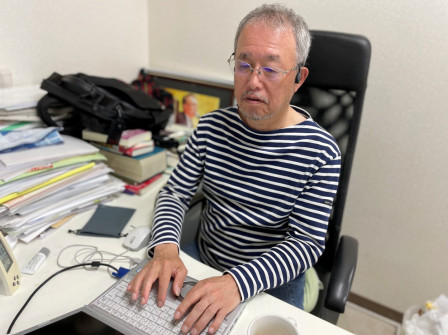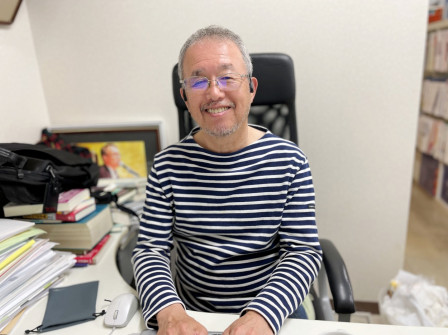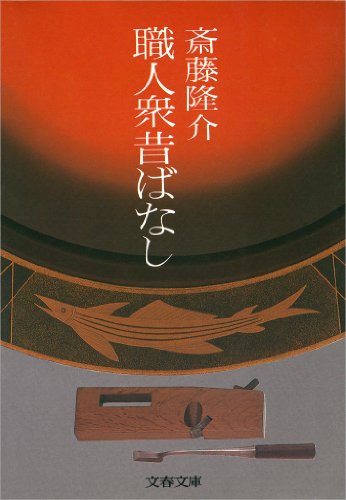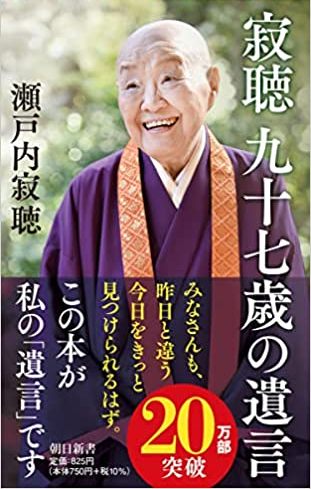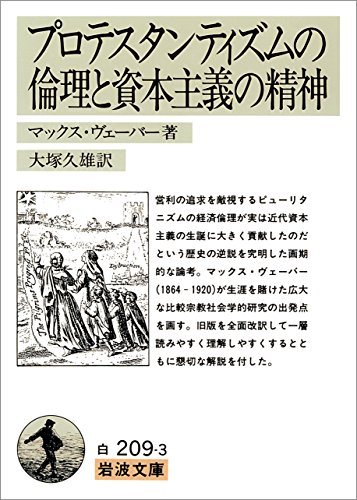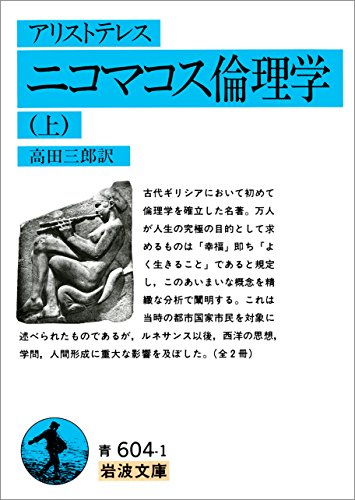2022年4月最後の日。
二月の雪、三月の風、四月の雨が、
輝く五月をつくる。
内館牧子さんのエッセイにある。
黄金週間の土曜日だけれど、
商人舎オフィスに出て、
原稿執筆と原稿手直し。
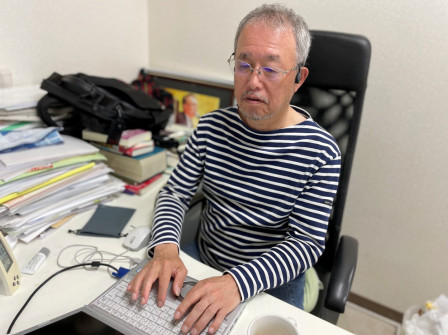
編集作業をして、
デザインの七海真理さんに入稿した。

疲れた。
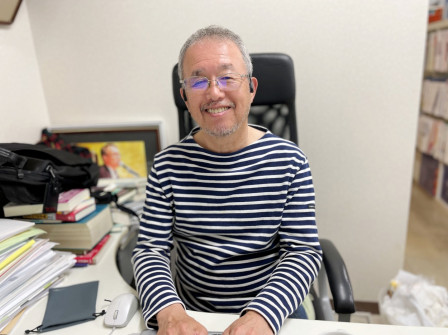
今日の朝日新聞「折々のことば」
第2365回。
やっぱり仕事は
命に
目立てをかける事なんだなァ
(土田一郎の父)
「鋸(のこぎり)目立て職人の父は、
親からもらった体は
減らないものと思っていたが、
鋸と同じで、
いい仕事をしようとつい酷使するうち
やっぱり細ってくると嘆いていたと、
跡を継いだ息子はいう」
「根を詰めればいやでもタコはできるし、
持病も出てくる」
「それでも人が働くのは、
命を削ってでもそれに
張りをもたせようとするからだ」
(『職人衆昔ばなし』から)
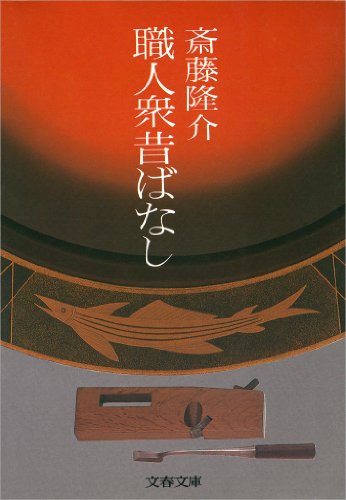
命を削ってでも、
商品に張りをもたせる。
売場や店に張りをもたせる。
本や雑誌、文章に張りをもたせる。
そのために人は働く。
今日の気分にぴったりだ。
今月の日経新聞に、
セブン&アイ・ホールディングスの、
組織や役員会についての、
署名記事が2本掲載された。
対照的で面白い。
セブン&アイにとっても、
これは有益だった。
ひとつの原稿は今日の記事。
「セブン&アイ、外国人が社長になる日」
論説委員の中村直文さんが書いた。
ふたつめは4月15日に発表された記事。
「セブン&アイ、逆三角形の組織図の思想を保てるか」
編集委員の田中陽さんの筆。
中村記事はこう始まる。
「セブン&アイ・ホールディングスの役員は
かつてこう話していた」
この語り口は、
新聞記者や雑誌記者がよく使うが、
私は嫌いだ。
名前を明かさない裏話。
その匿名の役員は言う。
「投資家やアナリストの話ばかりを聞いていたら、
経営革新なんてできないよ」
これは、その通り。
しかしこれ、
言ったのは鈴木敏文さんだと、
私は推測する。

「そんな同社が米アクティビスト(物言う株主)の
バリューアクト・キャピタルなどの声を受け、
取締役の過半を社外人材にする。
隔世の感がある」
そのあとに鈴木さんの記述がある。
「セブン&アイは少なくとも
6年以上前までは自信に満ちていた。
創業者の伊藤雅俊氏による
イトーヨーカ堂の業務改革、
鈴木敏文氏が主導したセブンイレブンの導入など、
日本の流通業界をけん引し続けてきた」
この表現は厳密に言えば間違っている。
業革もセブン-イレブンも、
伊藤さんが容認して、
鈴木さんが実行した。
「外部から招いた
サラリーマン経営者の鈴木氏を
絶対的なリーダーとして、
2005年にイトーヨーカ堂から
セブン&アイへ社名変更まで認めたことも
実に革新的だ。
創業一族の”イトー”(伊藤)を
表看板から消したわけだから」
これもニュアンスが違う。
鈴木さんは「外部から招」かれたわけではない。
若いころに東販を辞めて、
イトーヨーカ堂に転職しただけだ。
あとは自力でのし上がった。
「かつて役員が語ったように、
鈴木氏は二番煎じを嫌い、
誰もが反対してきた事業で
成功を収めたとの自負が強かった」
ここで「かつての役員」は鈴木さん自身だから、
これは鈴木さんが自分を語ったものだ。
「恐らく鈴木氏自身が内部にいながら
“アウトサイダー”という
自覚があったからだろう」
中村記事は、
鈴木=アウトサイダー、
=外国人取締役⇒外国人社長と、
ストーリーが続く。
そしてこれが結論。
「カギを握るのは”27億の男”と呼ばれる人物だろう」
「セブン&アイの取締役にして、
米セブン-イレブン社長の
ジョセフ・マイケル・デピント氏だ」
週刊誌的な記事だ。
「デピント氏は02年に入社し、
米国事業の基盤を固めてきた。
直近の報酬は約27億円で
井阪隆一セブン&アイ社長の約20倍を手にしている」
一方の田中陽原稿の冒頭は、
「セブン&アイは取締役会の過半数を
社外メンバーにする方針だ」
同じテーマ。
「先進的なガバナンス体制をつくります」
井阪隆一社長が力を込めて語った。
しかし田中原稿の主役は、
創業者の伊藤雅俊さんだ。

一般の会社組織は、
「三角形の樹形図」のようになっている。
頂点に株主や株主総会が構える。
その下には会長や社長、
その下に総務部、人事部、営業部、
企画部などが横並びで配置される。
さらに一段下がって、
三角形の底面には各部の課や室や研究所などが
末広がりにぶら下がる。
それに対して、セブン&アイの組織は、
「逆三角形」になっている。
「まず最上部は、
全国にある店舗や地域が横一線に並ぶ。
その下には店舗や地域のオペレーションを支える部署、
その下に本社や本部の管理部門がある。
そして逆三角形の下の部分には
社長(会長)があり、一番下には取締役会、
そして株主」
「”お客さま”は最上位の位置づけだ」
これは伊藤さんの考え方だ。
田中原稿は、
伊藤さんの30年以上も前のコメントを書く。
「会社の利益の源泉は
お客様の買い物金額から生まれます。
そこから、仕入れ先への支払い、
従業員への給料や賃料などに使い、
残ったお金を株主への配当に回します。
だから一番、偉いのは
お客様や地域の皆さんなのです」
この逆三角形の組織図が導入されたのは
1968年だった。
1978年、イトーヨーカ堂は、
日本企業として戦後初の無担保社債を
米国で公募発行した。
この時の伊藤さんの感想。
「企業として下着まで脱がされた気がした」
伊藤さん、いい表現するねぇ。
そして田中さんもよく覚えているねぇ。
伊藤雅俊さんの述懐。
「上場すると内なる規律と
外からの規律に縛られる」
「そんなセブン&アイHDが、
消費者(お客様)から遠い取締役会に
外部人材を多く登用する」
そして田中陽、渾身の一言。
「そこに魂は入るのか」
「決算発表の翌日のセブン&アイHDの株価は
強烈な売りを浴びせられた」
「おそらくヨーカ堂やセブン-イレブンで
買い物もしたことがないような
海外の投資家などから学ぶことが
どれほどあるのか」
同感だ。
日経新聞の二つの記事は、
対照的だ。
一方は鈴木敏文の言葉を、
匿名性を出し入れして書かれる。
一方は伊藤雅俊の述懐を、
掘り起こしつつ綴られる。
27億円の男が社長になるか。
それとも、
お客様を最上位にした組織が蘇生されるか。
私の答えははっきりしているが、
セブン&アイも「解」を求めておくべきだ。
命を削ってでも、
張りをもたせる会社と組織が、
つくられねばならない。
〈結城義晴〉