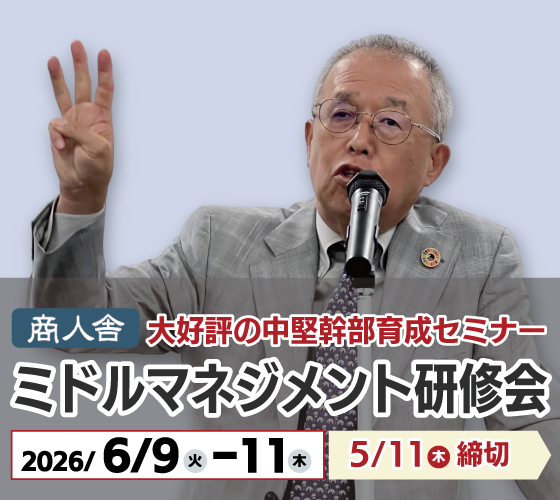このところ、
あっちへ行き、こっちへ戻りで、
慌ただしかった。
秋空だが、暑い。

名物の8番パー3。
バックティーからは、
下りの200ヤード。
いいスイングは、素振りです。

1日中、体を動かして、
満足のラウンド。
上り線のトンネルに入ったところで、
5台ほどの車の玉突き事故。
レッカー車2台がトンネルに入って行ったが、
それでは足りなかったらしい。
車線規制されて、
事故車はまだ2台残っていた。
日経新聞の「社説」が取り上げた。
「ユニクロ米国進出20年の示唆」
「ファーストリテイリング傘下のユニクロが、
米国に進出してから9月で20年になる」
ああ、もう20年か。
「高品質で価格を抑えた日本発ブランドとして
激しい競争に耐えて市場に浸透した」
海外展開する日本企業は、
歴史的に自動車や家電などの、
ハードライン製造業が中心だった。
ソフトラインやフードのなかで、
ユニクロはモデルとなった。
ユニクロの海外事業。
2024年8月期に20カ国超で1698店。
店舗数は日本国内の2倍を超える。
営業利益は2834億円。
国内の成績を8割上回る。
地域別に見ると中国が収益を支える。
一方、米国は長く赤字が続いた。
しかし22年8月期に黒字化した。
社説子。
「世界で通用する日本企業の特質を見極め、
東レと共同開発した機能性素材など
長期戦略の中で品質を継続的に磨いた」
「課題であったグローバル経営を担える人材も
社内で粘り強く育ててきた」
「海外で成長を目指す企業にとって示唆は多い」
ん~。
指摘が浅すぎる。
「規模拡大を図る米国で直面する問題は、
トランプ政権の高関税政策だ」
「製品は東南アジアなどから調達しているため、
コスト負担が重くなる可能性がある。
消費動向に合わせ値上げを含めて
機動的に価格を見直すとともに、
デジタル技術で、
需要予測と商品調達の精度を
向上させることも必要になろう」
文章があっちへ飛び、こっちへ帰る。
「世界各地で衣料品を扱う
ネット専業企業が勢いを増しており、
ユニクロも電子商取引の一段の強化が不可欠だ」
先刻ご承知。
「現在76歳の柳井氏がいずれトップを退いた後、
安定した経営を続けられるかも焦点となる。
社内外で想定される変化に対応できるよう
巨大化した組織の柔軟性が問われる」
せっかく社説で取り上げてくれたが、
何が言いたいのかわからない。
同じ朝刊の7面にやはりユニクロの記事。
「ユニクロ売上高、国内1兆円超え」
これは8月末決算発表の速報。
2025年8月期の連結売上高は、
3兆4000億円で前の期比10%増。
純利益4100億円で10%増。
ともに過去最高。
世界のアパレル業界首位は、
「ZARA」インディテックス(スペイン)。
25年1月期売上高が386億3200万ユーロ、
約6兆7000億円。
2位スウェーデンのH&Mの24年11月期は、
2344億7800万スウェーデンクローナ、
約3兆7000億円。
こちらは射程内に入った。
2018年には米国のギャップを追い抜いた。
柳井さんがかつて言っていた。
ZARAのラテン民族の感性には、
なかなか追いつくのが難しい。
H&Mの仕組みや理屈は、
キャッチアップできる。
その通りになりそうだ。
ユニクロは2001年に英国に進出した。
懐かしい。
昨2024年8月期に海外事業の売上収益が、
全体の55.2%に達した。
特に中国は店舗数が902店で日本を上回る。
24年8月期の決算では、
首位が国内ユニクロ事業の30%。
グレーターチャイナの売上収益が2位で21.8%。
3位のアジア、オセアニア17.4%。
中国は足元で消費の落ち込みが懸念されている。
それでも柳井さんは、
「売上高10兆円」を掲げる。
社説では日本のアパレル小売業が、
10兆円企業を目指すことをこそ、
書いてほしかったと思う。
いつになるかはわからないが。
実際にマンハッタン5番街を見ると、
ユニクロは正々堂々、
ZARAやH&Mを凌駕している。
この正々堂々ぶりは、
「Japan as Number One」の時代以来のことだ。

著者のエズラ・ヴォーゲルは、
2020年12月のコロナのなか、
90歳で逝去してしまったが、
日本人の学習意欲と読書習慣を褒めてくれた。
柳井さんも読書家だ。
それが私たちの強みだと、
あらためて認識するものだ。
〈結城義晴〉