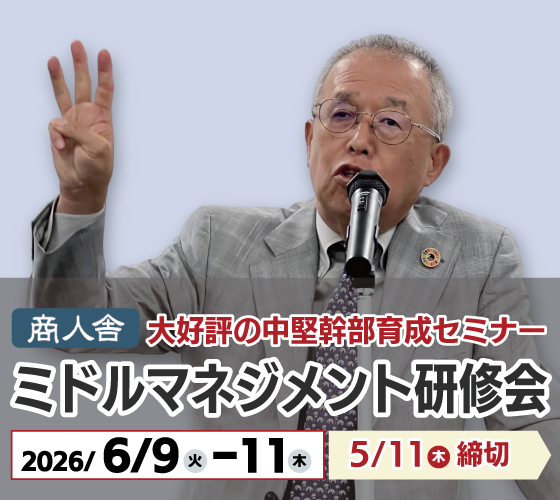第1回商人舎バイヤーセミナー。
8時15分から30分間。
昨日の結城義晴と鈴木哲男講師から5つの設問。

ただしすべてが記述式。
自分が理解したことを、
自分の言葉で回答してもらう。
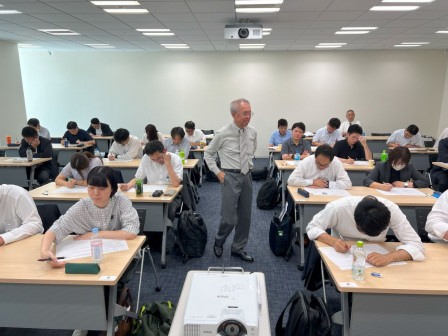
改めてテキストの内容を確認する。
そうすることで、理解はさらに深まる。
鈴木先生の講義の内容も、
私の見解を加えて解説させていただく。
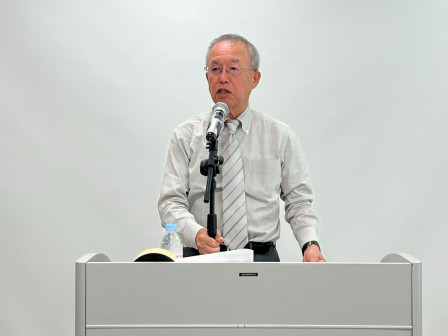
私の本来の講義は、
競争のマーケティングから、
分析手法まで。
ヘンリー・ミンツバーグのSWOT分析、
ボストン・コンサルティング・グループのPPM分析。
バイヤーの分析手法は多様だが、
その基本のキを教える。

午前中の第2・3講義は、
中村徹講師が担当。
商人舎のセミナーでは初めて、
登壇していただく。
1986年、大学院を修了して旧ジャスコに入社。
主にバイヤーとしてキャリアを積んだ。
1997年にSSM商品本部デイリーグループマネジャー。
そして南カリフォルニア大学のスクールで、
ブライアン・ハリス氏に学んだ。
そのカテゴリーマネジメントをジャスコに導入。
したがって前半の講義テーマは、
「バイヤーのためのカテゴリーマネジメント」
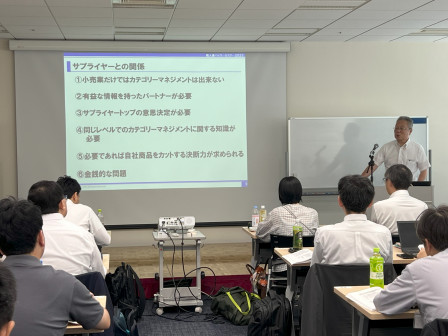
カテゴリーマネジメントの基本原則と考え方、
さらに取り組み方を事例を挙げて説明してくれた。

商品のカテゴリーをビジネスユニットと設定し、
サプライヤーに協力してもらって、
全体最適を追究する。
それによって顧客のニーズが満たされ、
売上げや利益が最大化される。
アメリカでは盛んに活用された。
そのセオリーとメソッドのエッセンスを、
丁寧に解説してくれた。
最後はクロスABC分析の活用法。
とても良かった。
第3講義のテーマは、
「バイヤーのための数値管理と計数管理」

バイヤーにとって肝要な数値の解説。
それとともにバイヤーの技術を、
一つ一つ説明してくれた。
仕入れ先を検討するときのポイント、
ブレーンの重要性なども指摘した。

バイヤーとしてのキャリアの中で得た知見。
それを披露してくれた講義だった。
参加者からは拍手が沸いた。

山本恭広編集長も駆けつけた。
中村さんは土谷美津子さんと同期入社だそうだ。
現在のイオン㈱商品物流担当副社長。
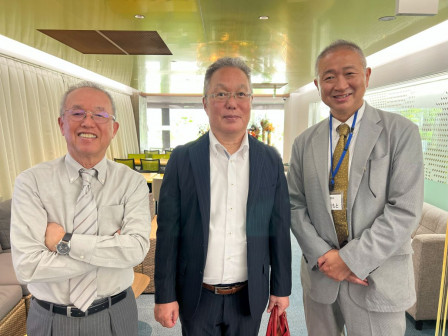
今後も商人舎で活躍願うことになる。
昼食を終えると、
いよいよ午後の講義。

プライベートブランドに関して、
体系的な講義をした。
そのグローバルな正式分類は、
コモディティ化現象によって生まれた。
だから4つの分類ごとに、
開発のコンセプトと手法は、
変わってこなければならない。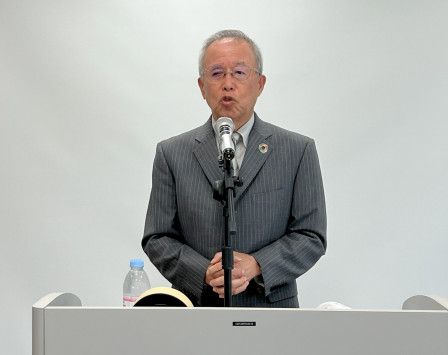
さらにバーチカルマーチャンダイジングの方法。
難しい勘所の解説は今、誰もしていないと思う。
そのなかで必須の仕様書発注の項目、
プライベートブランドのポジショニング、
デュアルブランド戦略。
アパレル問題も整理して、
最後はサプライチェーンマネジメントと、
バイヤーの情報提供。
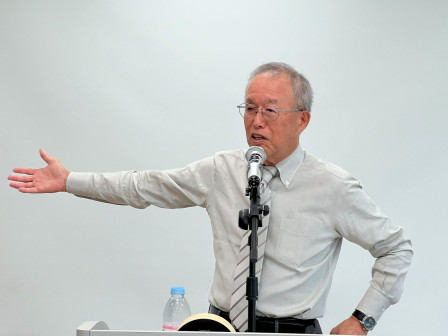
追加講義として、
バイヤーのコミュニケーション。
これはミドルマネジメント研修から、
一つだけ抜き出した。
バイヤーはチームのメンバーだけでなく、
多くの取引先とも、そして店舗とも、
コミュニケーションの達人でなければならない。
一通り講義を終えて、
最後の提案。
バイヤーとマーチャンダイザーは、
機能分化していかねばならない。
その機能分化と両利きの経営が、
シンクロしている。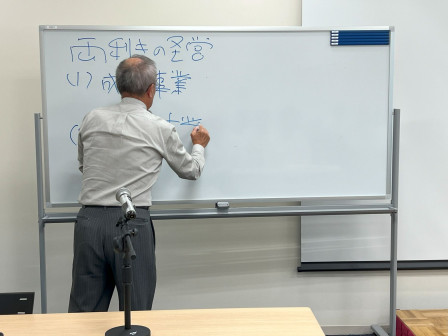
バイヤーは成熟事業の「深化」を推進し、
マーチャンダイザーは振興事業の「探索」を追究する。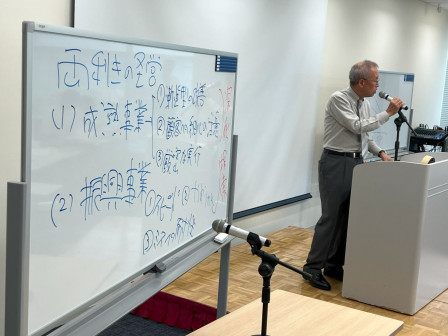
これが商人舎バイヤーセミナーの提案だ。
トップや幹部の皆さんも、
商品部対策として検討してほしい。
全員が真剣に受け止めてくれた。
30人規模の研修会には、
講師と受講生の結びつきが生まれる。
それが何より成果を上げる。
バイヤーは「稼ぎ屋」である。
これは故渥美俊一先生の説明の仕方。
私も同感している。
つまり商品部は顧客の満足をつくると同時に、
小売企業の成長を担う機能を果たす。
バイヤー諸君はその役割を重く受け止めて、
研鑽してほしい。
鈴木哲男、中村徹、
そして結城義晴。
2日間の講義のご清聴を感謝したい。
〈結城義晴〉