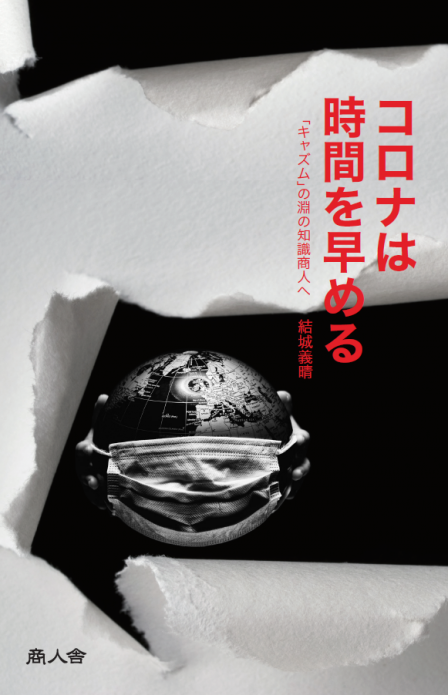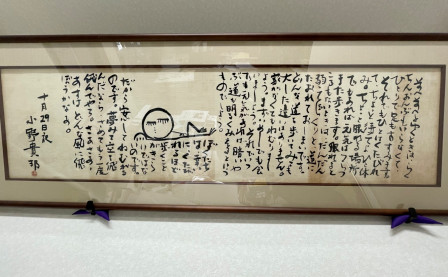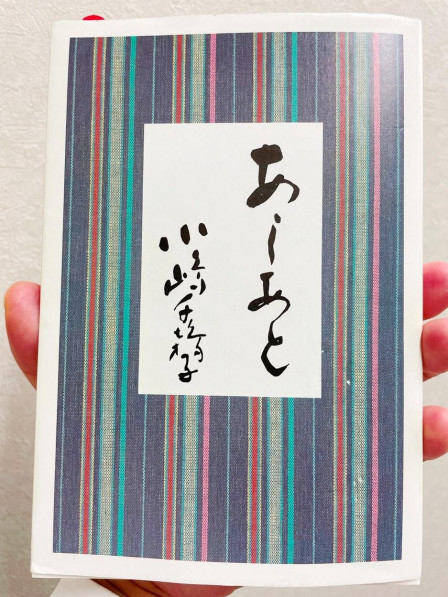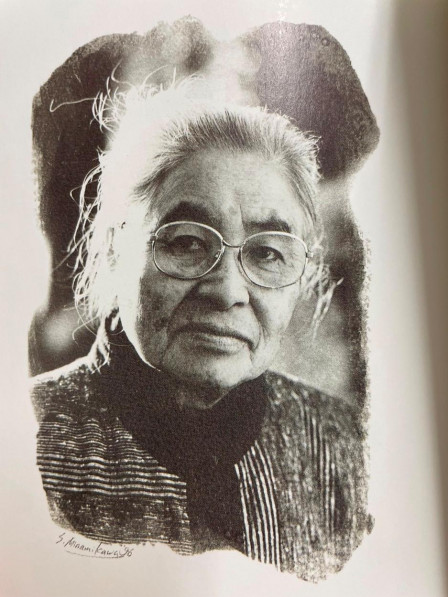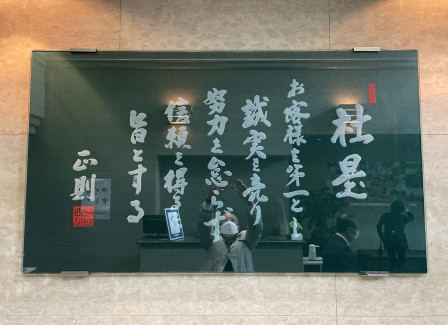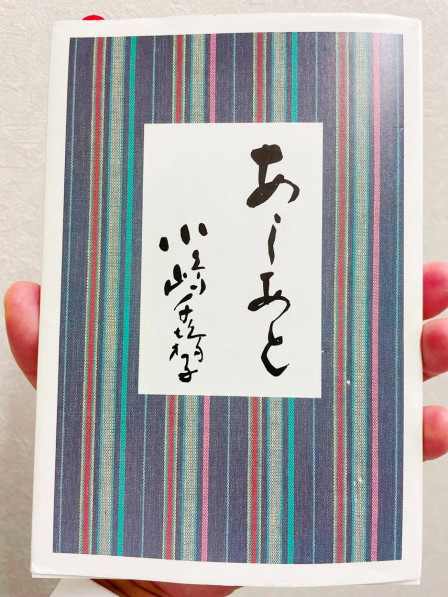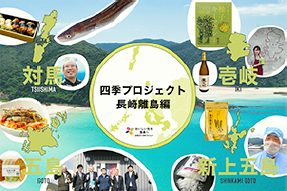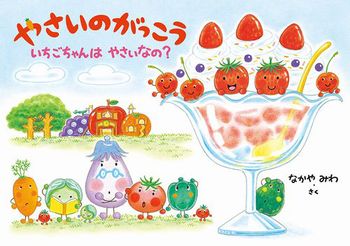Everybody! Good Monday!
[2022vol㉒]
2022年第22週。
そして5月最終週。
週中の水曜日から、
もう6月に入る。
自分が年を取ってきたからか、
それともコロナ禍によるものなのか、
時間は早まるばかりだ。
子どものころの時間は、
なんと長かったことよ。
昨日の日曜日は、
栃木県高崎市で35度を超えた。
もう、日本に夏がやってきている。
そしてウクライナにも、
夏は待ち受けている。
東部のルガンスク州で激しい交戦。

拠点都市セベロドネツク市では、
民間人死者数が1500人に及んだ。
私たちは平和の中にいるけれど、
ウクライナはまだまだ、
戦争の真っただ中にある。
あれだけ騒いでいたマスメディアも、
報道はやや沈静化して、
Twitterをはじめとするネットばかりが、
ゴミ箱の中に投げ捨てるように、
言葉を吐き散らす。
糸井重里さんのエッセイ。
「今日のダーリン」

「疲れているときには、
インターネットと少し距離を置く」
同感。
「インターネットには、
“言おう””聞け””読め”という意思が
たっぷり込められているので、
どうしたってまずは情報量全体が
多くなってるんですよね」
「そして、一般的に、人間が
ある程度はこころに持っている
“悪意”とか”失礼”とか
外では出さないはずの感情も、
ネット上では遠慮もなく
出しちゃっていますよね」
私はそれをできる限り避けているけれど。
「ネットの世界では
相手の顔も見えないことだし、
じぶんの存在も隠せるし、
言いやすいんですよね」
blogやFacebookというよりも、
匿名性の強いTwitterなどだろうね。
「それは”ホンネ”とか
呼ばれがちだけれど、
濾過してない”溜まり水”
みたいなものじゃないかなぁ」
その通りだ。
このあとのたとえ話が秀逸。
「昔、ある時代まで、
駅のあちこちに
痰壺(たんつぼ)というものが
備え付けられてました。
白いホーローの缶で
出来ていたものだったかな」
「そこに人がぺっぺと
“痰”を吐いていたんですよね」
「人間、痰がでるのも別に
めずらしいことじゃないんだし、
もちろん、置いてあるのだから
吐いていいんですが、
それはそれであんまり
見たいものじゃないし、
仕事として掃除をしていた人も
たいへんですよね」
「いまは、痰壺そのものが
なくなりましたが、
人間の痰そのものは
なくなっているわけじゃない」
「ネットの世界は、
まだ痰壺の時代なのかもしれない」
その通りだと思う。
「つまずいて転がさないように
気をつけないとねー」
さすが糸井重里。
あらためて見直した。
「人の前でも言えるようなことを言う。
これを原則にしたいな」
大賛成だ。
ウクライナの問題にしても、
ロシアや中国に対しても、
人の前でも言えるようなことを言う。
いつも冷静に見続ける。
煽り立てるようなことはしない。
そしてこれに乗じて自分を誇示しない。
自身の考え方として、
正々堂々と言うことは言う。
けれど正義を貫く。
今日は午前中、
オンライン会議。
第一屋製パン㈱の臨時取締役会。
チェーンストアのスクラップ&ビルド。
何かをビルドするために、
何かをスクラップする。
その考え方は小売業だけでなく、
製造業にも卸売業にも必要だ。
そしてシンプルに、スピーディーに、
これを成し遂げる。
いわば新陳代謝である。
スクラップしたものは、
必ず何かに利用される。
時代はまたそれを求めている。
ランチは岡野町に出た。
商人舎オフィスそばを流れる新田間川。
そして遊歩道。

森林浴とまではいかないが、
いい気分だ。

木々にも葉々にも勢いがある。

日本自生の額紫陽花(ガクアジサイ)。
こちらは本紫陽花(ホンアジサイ)。
夏には夏の花。
今週は月刊商人舎6月号の入稿の週。
頑張ります。
私がいつもボトルネックになっている。
みんなに迷惑をかけている。
反省しつつ、
頑張ります。
言い訳を言わず、
頑張ります。
いくつになっても、
頑張ります。

では、みなさん、
今週も、正々堂々、正義を貫こう。
Good Monday!
〈結城義晴〉